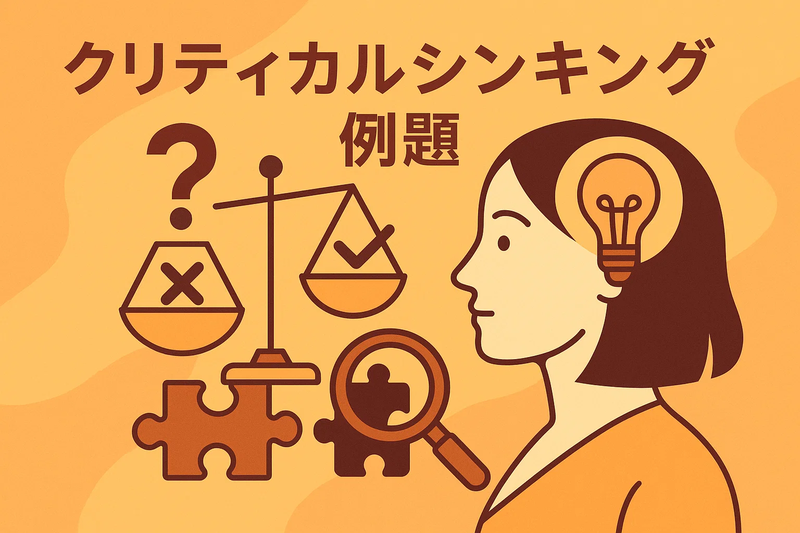
はじめに
「クリティカルシンキングって具体的にどういう思考法なの?」 「ロジカルシンキングやラテラルシンキングとは何が違うの?」 「実際のビジネスでどう役立つの?」
といった疑問を持つ方のために、この記事ではクリティカルシンキングの基本から具体的なステップ、事例を交えた実践方法、さらに研修に導入するメリットまでをわかりやすく紹介しています。
ぜひ参考にしていただき、日々の業務や人材育成に活用ください。
- はじめに
- クリティカルシンキングとは
- クリティカルシンキングのステップ
- クリティカルシンキングのケース
- ロジカルシンキングやラテラルシンキングとの違い
- クリティカルシンキングを研修で導入するメリット
- クリティカルシンキングの研修をするならWisdomBase
- まとめ
クリティカルシンキングとは
 クリティカルシンキング(批判的思考)とは、与えられた情報をそのまま受け入れるのではなく、前提を疑い、根拠や背景を論理的に検証しながら最適な答えを導き出す思考法です。
クリティカルシンキング(批判的思考)とは、与えられた情報をそのまま受け入れるのではなく、前提を疑い、根拠や背景を論理的に検証しながら最適な答えを導き出す思考法です。
単に否定することではなく、事実を整理し、多角的に可能性を検討する力が求められます。ビジネスや学習の場面で役立ち、柔軟で正確な判断を支える大切なスキルです。
クリティカルシンキングのステップ
 クリティカルシンキングは、物事を正しく理解し、適切な解決策を見つけるための思考法です。例題を解く前提として、思考の進め方をステップごとに整理してみましょう。
クリティカルシンキングは、物事を正しく理解し、適切な解決策を見つけるための思考法です。例題を解く前提として、思考の進め方をステップごとに整理してみましょう。
事実と意見を分ける
第一のステップは「事実と意見を分ける」ことです。例えば「クレームが増えている」というのは事実ですが、「担当者の対応が悪い」というのは意見に過ぎません。
この二つを区別しないと、思い込みに基づいた誤った結論を導いてしまいます。まずはデータや記録など、動かしようのない事実を押さえることが大切です。
前提を疑う
次に「前提を疑う」ことが欠かせません。人はどうしても「きっとこうに違いない」と思い込みを持ちがちですが、クリティカルシンキングではそれを意識的に外していきます。
「担当者のせいだ」という前提をそのまま受け入れるのではなく、商品の品質、説明不足、価格設定、サービスフローなど他の要因を検討する必要があります。
複数の視点を持つ
三つ目のステップは「複数の視点を持つ」ことです。問題を一方向から見るのではなく、顧客、上司、現場スタッフ、経営者といった異なる立場から状況を捉えると、新たな気づきが得られます。
顧客にとっては説明不足が原因でも、スタッフから見ればマニュアルの不備が原因かもしれません。多角的に視野を広げることで、より妥当な判断に近づけます。
根拠を検証する
四つ目は「根拠を検証する」ことです。思いつきや感覚で結論を出すのではなく、データや具体的な事例をもとに判断します。
例えばクレームの件数推移や内容の傾向を調べれば、単発的な問題なのか、長期的な傾向なのかが見えてきます。ここでの検証作業が、曖昧な議論を避け、納得感のある結論につながります。
最適な結論を導く
最後に「最適な結論を導く」ステップです。表面的な原因だけを取り上げるのではなく、データや複数の視点を踏まえて本質を見極めます。
そのうえで、改善策をデザインし、実際に行動につなげていくことが求められます。この結論は単なる意見ではなく、論理と根拠に裏付けられた「納得感のある答え」となります。
クリティカルシンキングのケース
 クリティカルシンキングは、目の前の出来事を単純に「原因はこれだ」と決めつけるのではなく、複数の角度から検証して最適な解を導く力です。
クリティカルシンキングは、目の前の出来事を単純に「原因はこれだ」と決めつけるのではなく、複数の角度から検証して最適な解を導く力です。
【例題1】クレーム対応のケース
例えば【例題1】クレーム対応のケースを見てみましょう。会社で「顧客からのクレームが増えている」との声が上がったとき、多くの社員は「担当者の対応が悪いからだ」と結論づけがちです。
しかし、果たしてそれだけが原因でしょうか。商品の品質低下や説明不足、価格設定の問題など、別の要因が潜んでいる可能性はないか検討が必要です。さらに、クレーム件数の推移や内容の傾向をデータで確認しなければ、本当の全体像は見えません。
もしかすると一部の顧客の声を全体と誤解している可能性もあります。こうした「問い直し」を通じてバイアスを外すことこそ、クリティカルシンキングの第一歩です。
【例題2】業務改善の課題
次に【例題2】業務改善の課題を考えます。「業務がうまくいかないのは手順変更が急だったから」という意見が出た場合、単純に納得するのではなく立ち止まることが大切です。
「本当に急な変更だけが原因なのか? 手順そのものに非効率さがなかったか?」「 変更前と後で成果やパフォーマンスにどのような違いが生じたのか? 」こうした視点で事実を確認し、仮説を比較検証することで、課題の本質に迫ることができます。
つまり、クリティカルシンキングとは「思考の幅を広げ、根拠を基に判断する習慣」を持つことです。
これにより、感覚や先入観に左右されず、より確実で効果的な解決策を導けるようになります。
【例題3】就活・面接で問われる「筋道のある答え方」
面接でよくある質問として「残業時間が多い部署を改善するには?」がありますが、「人を増やすべき」という即答は単純すぎて、深い思考を示すものとは言えません。ここで重要なのは、まず業務量の分析を行い、何が残業を引き起こしているのかを把握することです。
そのうえで「ツール導入による効率化」「役割分担の見直し」「業務フロー改善」といった複数の解決策を提示し、それぞれのメリットとデメリットを比較しながら結論を導くと、より筋道のある答えになります。
このプロセスを踏むことで、単なる思いつきではなく、論理的に裏付けられた回答ができ、面接官にも「思考力と問題解決力を持つ人材」として評価されやすくなります。クリティカルシンキングは、就活の場面でも大きな武器になるのです。
【例題4】年齢だけで決められないークリティカルシンキングで見るオリンピック
クリティカルシンキングを用いて「高齢でもオリンピックに出場できるのか?」という問いを考えると、一概に不可能とは言えません。実際には、60歳以上の選手がオリンピックに出場した例が存在します。
参考: https://sports.yahoo.co.jp/official/detail/2024072900020-spnaviow
特に乗馬競技では、年齢制限が比較的緩やかで、体力だけでなく技術や経験が重要視されるため、高齢でも活躍できるといえるでしょう。例えば、乗馬競技においては60歳を超える選手が出場し、国際舞台で競技を行った事例があります。
このことから、成人でも、特に高齢者であっても、適した競技であればオリンピックへの出場が可能という結論になります。 ただし、多くの競技では若年層の出場が圧倒的に多いのが現状であり、競技特性や体力面の要件も考慮する必要があります。したがって、クリティカルシンキングでは、「年齢だけで出場の可否を断定できない」という柔軟な視点が大切です。
ロジカルシンキングやラテラルシンキングとの違い
 クリティカルシンキングと混同されやすい概念として、ロジカルシンキングとラテラルシンキングがあります。それぞれの特徴を整理すると違いが明確になります。
クリティカルシンキングと混同されやすい概念として、ロジカルシンキングとラテラルシンキングがあります。それぞれの特徴を整理すると違いが明確になります。
まずロジカルシンキングは、既存の情報を整理し、筋道立てて結論を導く方法です。例えば売上低下の原因を「客数減」と「単価減」に分け、それぞれを論理的に検証していくのが典型的な進め方です。
一方、ラテラルシンキングは固定概念を外し、発想を飛躍させる思考法です。従来の枠組みでは考えつかないアイデアを生み出すのに役立ち、新しいビジネスモデルやユニークな商品の開発などに強みを発揮します。
例えば「電動歯ブラシ」は、最初は手で磨くものという常識を覆しました。歯を動かすのではなく、ブラシを振動させて自動で汚れを落とすという逆転の発想です。
さらに近年では、アプリと連携して磨き方を可視化するなど、まったく新しい体験価値を生み出しています。これに対しクリティカルシンキングは、提示された情報や前提をそのまま受け入れるのではなく、「本当に正しいのか?」と根拠を疑い、妥当性を検証する姿勢に重きがあります。
つまり、ロジカルシンキングが筋道を整えるツールであり、ラテラルシンキングが発想を広げるツールだとすれば、クリティカルシンキングはそれらを使う前に「思考の質を磨くためのフィルター」として機能します。
クリティカルシンキングを研修で導入するメリット
 クリティカルシンキングは、ビジネスの現場だけでなく教育や人材育成の場面でも大きな価値を持つ思考法です。
クリティカルシンキングは、ビジネスの現場だけでなく教育や人材育成の場面でも大きな価値を持つ思考法です。
特に企業の研修に導入することで、組織全体の課題解決力や意思決定力を底上げし、持続的な成長につなげることができます。
以下では、研修でクリティカルシンキングを導入するメリットを具体的に紹介します。
問題解決力の強化
多くの組織では、目の前に現れた課題に対して「表面的な原因」だけを解決してしまうケースが少なくありません。多くの組織では、目の前に現れた課題に対して「表面的な原因」だけを解決してしまうケースが少なくありません。
例えば「社員の離職率が高いのは給与が低いからだ」と短絡的に考えてしまうと、実際には「評価制度の不透明さ」や「上司とのコミュニケーション不足」といった、より深い要因を見落とすことになります。
クリティカルシンキングを学ぶことで、研修参加者は「本当にそれが原因なのか?」「他に要因はないか?」と前提を疑い、複数の可能性を検討する習慣を身につけられます。 これにより、問題の核心を捉えた解決策を導き出せるようになり、組織の改善力そのものが強化されます。
チーム内コミュニケーションの改善
職場の会議や日常業務では、感情的な発言や思い込みによる衝突がしばしば発生します。意見の対立が「個人攻撃」へと変わってしまうと、チームの雰囲気は悪化し、協力体制が崩れてしまいます。
クリティカルシンキングは、意見を「正しいか・間違っているか」ではなく、「根拠があるか・妥当か」という観点で評価します。そのため、議論がより建設的になり、個人の感情に左右されない冷静な話し合いが可能になります。
研修でこうした姿勢を学んだ社員は、相手の意見を尊重しつつ、論理的に補足や改善案を提示できるようになるため、チーム全体の協働力が高まります。
意思決定の質向上
企業においては、日々さまざまな意思決定が行われます。新規事業の方向性、採用基準、業務プロセスの改善策など、その判断が組織の成果に直結します。 クリティカルシンキングを取り入れることで、社員は「一つの視点や意見」に依存せず、複数の立場からの見方を取り入れ、さらにデータや事例といった根拠を検証する習慣を持つようになります。
結果として、リスクを最小限に抑えつつ、より妥当性の高い意思決定ができるようになります。特に管理職やリーダー層にとって、このスキルは組織を方向づけるうえで不可欠といえるでしょう。
昇進試験やリーダー育成への直結
多くの企業では昇進試験やリーダー候補者の選定において、「論理的に説明できる力」「課題を多面的に分析できる力」が重要視されます。クリティカルシンキングを研修で習得することは、こうした評価項目に直結します。
例えば面接や試験で「部署の課題をどう改善するか」と問われた際、表面的な意見ではなく、複数の仮説を提示し、それぞれの根拠を比較検討した上で結論を導く姿勢を見せれば、高い評価につながります。
また、実際にリーダーとしてチームを率いる際も、メンバーの意見を整理し、根拠に基づいた方向性を示すことで、信頼を得やすくなります。
組織文化への波及効果
クリティカルシンキングの習慣が根付いた組織では、「なんとなく」「前例に従うから」という理由で意思決定が行われることが減り、論理と根拠に基づいた議論が自然と当たり前になります。 これにより、組織全体に「考える文化」が育ち、長期的な競争力の強化につながります。加えて、若手社員にとっては、自分の意見を裏付けとともに述べる訓練となり、上司や先輩に依存しすぎない主体的な行動力を身につけられるのも大きなメリットです。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
クリティカルシンキングの研修をするならWisdomBase
ノーマルタイプ
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
クリティカルシンキングなどの研修教材の管理にお困りでしたら、弊社が提供するeラーニングシステム 「WisdomBase」 をぜひご活用ください。WisdomBaseは、研修コンテンツをオンラインで配信・管理できる eラーニングシステム です。動画教材や確認テストなどを組み合わせて、受講者の理解度を可視化しながら効果的な学習運営を行えます。
クリティカルシンキングをテーマとした教材をWisdomBase上で配信すれば、実際のビジネス課題を再現した事例学習なども容易に実施できます。 これにより、単なる知識の習得にとどまらず、現場で活かせる実践的な思考力を身につける仕組みを構築できます。
また、オンライン対応により、時間や場所を選ばず受講可能。柔軟な人材育成を実現したい企業に最適です。eラーニングシステムの導入をご検討中でしたらお気軽にお問い合わせください。
wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
まとめ
クリティカルシンキングは、単なる知識ではなく実践的な思考習慣として身につけることで、その効果を最大限に発揮します。
事実と意見を分け、前提を疑い、複数の視点を持ち、根拠を検証したうえで結論を導くプロセスを繰り返すことで、問題解決力や意思決定力は確実に高まります。
さらに、チーム内での感情的な対立を減らし、建設的なコミュニケーションを促すため、組織文化の改善にも直結します。昇進試験やリーダー育成の評価基準とも密接に関わるため、人材育成においても欠かせないスキルです。
研修を通じて体系的に学び、日常業務に落とし込むことで、個人と組織の双方が成長できるでしょう。クリティカルシンキングは、未来を切り拓くための思考基盤です。

