
はじめに
「オンライン教材を作るにはどんな形がいいのだろうか?」
「教材の構成はどう組み立てれば受講者が続けやすいの?」
「Udemyなどのプラットフォームに出すべき?それとも自社で販売した方がいい?」
こうした疑問を持っている方のために、今回はオンライン教材の作り方をわかりやすく整理しました。
制作のステップから詳しく紹介し、また、失敗しやすいポイント、その回避策、さらに販売までの流れをまとめて紹介しています。
ぜひ参考にしていただき、自社に合ったオンライン教材の作成に役立ててください。
- はじめに
- オンライン教材とは
- オンライン教材にはどんなものがある
- オンライン教材を作成する4つのステップ
- 【ジャンル別】オンライン教材の作り方
- オンライン教材の作成に必要な準備・機材・ツール
- よくある失敗と回避策!オンライン教材 作り方で陥りがちなミス5選
- 差別化のポイント!ユニークな教材を作るためのコツ
- オンライン教材の将来性は高い
- オンライン教材を販売するならWisdomBase
- まとめ
オンライン教材とは

オンライン教材とは、学習者がインターネットを通じていつでもどこでもアクセスできる学習コンテンツと学習体験のことです。
動画・テキスト・音声といった複数形式を組み合わせ、受講者の学習目標に沿って部分ごとに分け、クイズや課題、フィードバック、コミュニティ支援まで含めて作成されます。
対面に比べて反復しやすく、進捗データをもとに継続的に改善できるのが大きな強みです。
オンライン教材にはどんなものがある
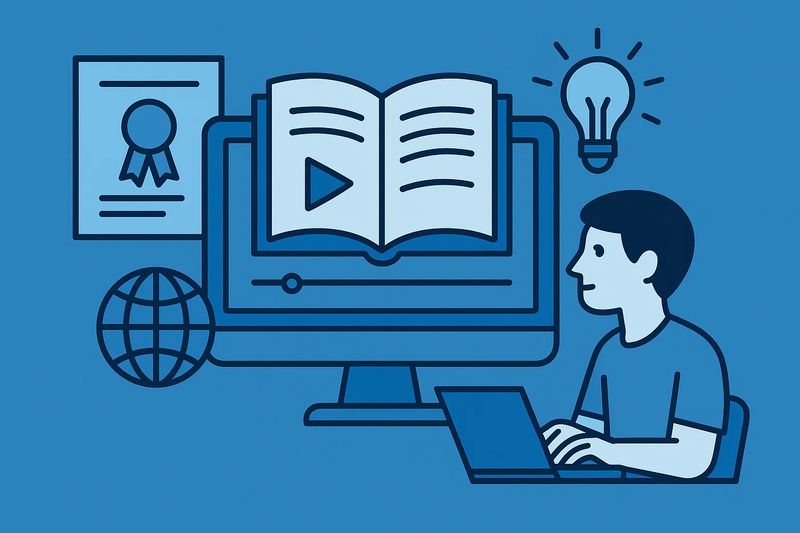
オンライン教材にはどんなものがあるのでしょうか。
動画
まず動画。実演や操作説明、思考プロセスの可視化に最適で、短尺(5〜10分)単位に区切り、字幕・チャプター・資料連携を行うと学習効率が上がります。音質が理解度を左右するため、マイクと静音環境の確保が大切です。
テキスト
次にテキスト。PDFやスライド、手順書、チェックリスト、演習ワークシートなどで、検索性・更新性に優れます。図解やテンプレートを用意するとすぐ使える価値が高まります。
音声
音声は通勤や家事の合間に学べるのが魅力で、要点の解説やコーチング、復習用に向きます。図やUI説明が必要な場合は、ノートやスライドの併用が効果的でしょう。
その他オンラインサポート
最後にその他オンラインサポート。ライブQ&Aや週次オフィスアワー、フォーラム、コミュニティ、課題添削、学習管理システム(LMS)による進捗可視化やクイズ、修了証の発行などが継続率を押し上げます。これらを目的から逆算してハイブリッドに設計することで、成果が再現しやすい教材になるはずです。
オンライン教材を作成する4つのステップ
 以下にて、オンライン教材を作成するための4つのステップを紹介します。
以下にて、オンライン教材を作成するための4つのステップを紹介します。
1 内容を決める
オンライン教材を作る第一歩は、どのような学習内容を扱うかを明確にすることです。対象となる受講者層、例えば、学生、社会人、初心者、中級者などを想定し、その人たちが「何を学びたいのか」「どのような課題を解決したいのか」をリサーチします。
例えば語学教材なら「日常会話を短期間で習得したい人」、資格取得教材なら「効率よく合格ラインを突破したい人」といった具体的なニーズを設定するのが大切です。
学習目標を明確にすれば、教材の内容は自然と絞られます。ゴールが「TOEICで700点を超える」「プログラミング基礎を30日で習得する」といった形で数値化できると、学習者にとって魅力的で分かりやすい教材になります。
2 構成を作る
次に、決めた内容を学習者が無理なく理解できるように整理し、構成を作ります。教材は一度にすべてを詰め込むよりも、段階を踏んで少しずつレベルアップできる形が理想です。
具体的には「導入編 → 基礎編 → 応用編 → まとめ」といった流れで段階的にして、それぞれのモジュールには短いレッスンや演習を組み込みます。
動画教材であれば1本5~10分程度に分割すると集中力を保ちやすく、テキスト教材であれば見出しや図解を入れることで読みやすさが向上します。
また、演習問題や小テストを入れると理解度を確認でき、学習者のモチベーション維持にもつながります。構成を設計する段階で「どこで演習を入れるか」「どこで復習を促すか」を決めておくことが成功のカギでしょう。
3 オンライン教材を実際に作る
構成ができましたら、実際の教材の作成に取りかかります。形式は大きく分けて動画・テキスト・音声があり、これらを組み合わせて教材を完成させます。
動画は理解を深める効果が高い一方で、撮影や編集の手間がかかります。スマートフォンと簡易マイクがあれば十分な品質を確保できるので、初心者でも挑戦しやすい形式です。
テキスト教材はPDFやスライド形式で提供でき、更新や配布がしやすいのが強みです。音声は通勤中や家事の合間でも学習できるため、復習用のサマリーや追加解説に活用すると効果的です。
さらに、Q&Aや添削などのオンラインサポートを組み合わせれば、学習者がつまずいたときにフォローでき、継続率を高められます。制作の段階では「分かりやすさ」と「使いやすさ」を重視し、映像や文章の品質、操作のしやすさ、デザインの統一感に配慮することが大切です。
4 オンライン教材を販売する
オンライン教材の販売方法には、以下の3つがあります。
- LMSを活用する方法
- マーケットプレイスを活用する方法
- 自社サイトにEC機能をつける方法
LMSとはLearning Management Systemの略で、教材の配信・受講者の管理・進捗確認・決済まで一元化できる仕組みです。効率的な運営とブランド力の強化に効果的だと言えます。
マーケットプレイスとは、Udemyのように既存の学習者基盤を持つプラットフォームです。集客力が強く初心者でも販売しやすいですが、価格や掲載規約の制約を受けやすいのが特長です。
自社サイトにEC機能を設けて販売する方法もあります。価格やデザイン、販売のスタイルを柔軟に選べる、自社ブランドを直接訴求できますが、集客は自力で行う必要があります。
特にオススメなのが「LMSを活用する方法」です。運営に必要な機能を一括で利用でき、効率化と信頼性を両立できるためです。また、長期的な収益化やリピーターの獲得に最適でしょう。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
【ジャンル別】オンライン教材の作り方

オンライン教材は、対象とする学習者や目的によって設計や工夫の仕方が大きく異なります。ここでは、代表的な5つのジャンルに分けて、それぞれに適したオンライン教材の作り方を紹介します。受講者のニーズに合わせて設計すれば、学習効果と満足度の高い教材を提供することができるはずです。
受験対策オンライン教材
受験対策教材の最大のポイントは「高得点を取るための効率的な学習」です。出題傾向の分析に基づき、頻出問題を重点的にカバーする必要があります。
教材は、「基礎解説 → 演習問題 → 模試形式」といった流れで構成すると効果的です。動画による解説は、難解な内容を図や板書風に説明することで理解を深めやすく、テキストやPDF形式で問題集を提供することで復習もしやすくなります。
さらに、模擬テストや小テストをオンラインで行い、自動採点や解答解説を即時に提示する仕組みを整えると、学習者は弱点を効率的に把握できます。
学習計画を可視化できる進捗管理システムも導入すれば、受講者が挫折せずに続けやすい環境を作れるでしょう。
幼児向け・家庭教師型オンライン教材
幼児教育向けの教材は「楽しく学ぶ」ことが最優先です。文字や数字の基礎を覚える段階では、動画や音声にキャラクターや歌を取り入れると集中力を保ちやすくなります。短時間で区切ったコンテンツや、タッチ操作やクイズ形式で参加できるインタラクティブ教材が効果的でしょう。
また、家庭教師型を意識するなら、ライブセッションや個別指導に近い仕組みを用意すると保護者の満足度も高まります。
保護者向けに学習の進捗レポートや声かけのアドバイスを提供する機能を組み込むと、家庭での学習サポートがしやすくなります。幼児向け教材では「安全性」「操作のシンプルさ」も重要で、複雑な操作を排除したデザイン性が求められます。
資格取得対策オンライン教材
資格試験の教材では「合格する、または合格ラインを突破する」ことが明確なゴールです。そのため、試験範囲の網羅性と効率的な復習機能がポイントになります。
教材はテキストや動画による体系的な解説に加えて、演習問題や過去問を大量に組み込み、自動採点・弱点補強の機能を持たせることが効果的でしょう。
特に資格試験は範囲が広いため、章ごとのミニテストや模擬試験を段階的に実施する仕組みが有効です。学習スケジュールをカレンダー形式で提示したり、進捗度に応じて「次にやるべき課題」を自動で提示する機能を追加すると、効率的に学習を進められます。
さらに、受験者同士で情報交換できる機会(Zoomでの交流会)や質問ができる場を用意すれば、学習者の不安解消やモチベーション維持につながることが期待できます。
語学学習向けオンライン教材
語学教材を作成する際には、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく鍛えられる教材がおすすめです。
特に英会話を学ぶ受講者の多くは、動画や音声を活用してリスニングやスピーキングに重点を置く傾向があります。字幕やスクリプトを併用すれば、初心者でも理解しやすい教材に仕上げることができます。
発音練習には、AIの音声認識を活用したフィードバック機能を取り入れると効果的です。また、テキスト教材として文法解説や例文集をPDFで提供すれば、学習者が復習しやすい環境を整えられます。
さらに、チャットボットやオンラインコミュニティを活用して、実際に言語を使う場を用意することも大切です。これにより「学んだ知識をすぐに実践できる」学習体験を提供できます。
加えて、短時間で繰り返し学べるクイズ形式の教材や、日常会話をシミュレーションできるロールプレイ型教材も人気が高く、受講者のモチベーション維持につながります。
プログラミング・デザイン学習向けオンライン教材
プログラミングやデザイン分野の教材は、実践を通してスキルを習得できることが大切です。座学中心ではなく、画面キャプチャやコードの実演動画を組み込み、受講者が自分の環境で手を動かしながら学べる構成にします。
課題を提出できる仕組みや、添削・フィードバックを受けられる環境を整えると成長が早まるでしょう。特にデザイン教材では、完成例とプロセスをセットで提示すると理解が深まります。
プログラミングではGitHubなどのリポジトリと連携し、コードレビューを受けられる仕組みを作ると実務に近い学習が可能です。学習進度に応じて「初級→中級→上級」とステップアップできる構成にすれば、受講者は達成感を得やすく、継続率が高まるはずです。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
オンライン教材の作成に必要な準備・機材・ツール

オンライン教材を作るには、単に知識を整理するだけでなく、それを高い品質で学習者に届けるための環境や道具を整えることが欠かせません。ここでは、最低限そろえておきたい準備や機材・ツールについて紹介します。
インターネット環境
まず大前提として、オンライン教材を作るために、安定したインターネット環境が必要です。教材の作成過程では大容量の動画ファイルをアップロードしたり、クラウド上で共同編集を行う機会が多くなります。Wi-Fiだけでなく有線接続を準備しておくと、アップロードやライブ配信時に回線が途切れるリスクを減らせます。また、通信速度は下りよりも上り(アップロード速度)が重要で、10Mbps以上を目安にすると安心です。
動画撮影・編集ツール
オンライン教材の中心になるのは動画でしょう。撮影用にはスマートフォンやデジタルカメラでも十分対応できますが、画質よりも音声の明瞭さが学習体験に直結するため、外部マイクの導入をおすすめします。
編集には無料の「DaVinci Resolve」や「CapCut」、有料の「Adobe Premiere Pro」などが使いやすいソフトです。不要な間や雑音をカットし、テロップや図解を挿入することで理解度を高められます。
画像編集ツール
教材を分かりやすくするためには、図解やイラストを効果的に取り入れることが大切です。無料の「Canva」や「GIMP」、本格的に作り込みたい場合は「Adobe Photoshop」などが利用できます。
特にスライド資料やPDF教材を作成する際には、シンプルで統一感のあるデザインが学習者の集中力をサポートします。
テキスト執筆ツール
解説文や補足資料、演習問題をまとめるための執筆ツールも欠かせません。代表的なのは「Microsoft Word」「Google ドキュメント」などですが、チームでの共同作業を考えるならクラウドベースのツールが便利です。
さらに、構成を管理したりスクリプトを作成する場合には「Notion」といったライティングツールを使うと効率的でしょう。
照明
動画教材を作成する際、意外と差が出るのが照明です。自然光でも撮影できますが、天候や時間帯に左右されやすいため、安定した品質を求めるならリングライトやソフトボックスライトの使用が望ましいです。顔や手元を明るく映すことで、学習者に与える印象が大きく変わり、信頼性の高い教材に見えます。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
よくある失敗と回避策!オンライン教材 作り方で陥りがちなミス5選

オンライン教材の需要は年々高まっていますが、実際に作成する際には多くの人が同じような失敗を繰り返しています。
ここでは特に陥りがちな5つのミスを取り上げ、それぞれの回避策を紹介します。これらを意識することで、学習効果と販売成果の両面で質の高い教材を提供できるでしょう。
1 教材内容があいまい
最も多いのが「結局この教材を学ぶと何ができるのかが分からない」という状態です。ゴールが不明確な教材は受講者に不安を与え、途中で離脱されやすくなります。
回避するためには、最初に「学習後に到達できる姿」を具体的に設定することです。例えば「TOEIC700点を目指す」「3か月でPythonの基礎文法を習得する」といった数値化された目標を掲げましょう。学習者はゴールが明確だと取り組みやすく、修了後の達成感も得られやすくなります。
2 受講者視点が欠けていて使いにくい教材設計になっている
作成者が「伝えたいこと」を中心に作ってしまうと、受講者にとっては使いにくい教材になるかもしれません。例えば、専門用語が多くて受講者は理解できない、1本の動画が長すぎたりすると集中力が続かないなどの問題があれば、学習効率は落ちてしまい、オンライン教材を作っても無駄になってしまいます。
大切なことは、「受講者の気持ち」を常に意識することです。作成するジャンルにもよりますが、動画は5〜10分程度に区切る、重要なキーワードは字幕やスライドで補足する、章ごとに演習や確認テストを入れるといった工夫が効果的です。
また、事前に想定学習者のレベルを調査し、初心者向け・中級者向けなど段階に分けて教材を設計すると「ちょうどよい難易度」で学べます。
3 著作権の問題
画像や音楽、文章を無断で使用してしまうのもよくある失敗です。販売・公開後にトラブルになれば信頼を大きく失い、販売停止や損害賠償のリスクにもつながります。
そのようなリスクを避けるには、著作権フリーの素材を利用するか、自作のコンテンツを使用することです。また、商用利用可能なフリー素材サイトを活用したり、AI生成ツールを利用する場合も利用規約を確認することが重要です。
引用を行う際は出典を明示して、教材全体のオリジナリティを高めるよう心がけましょう。
4 価格設定のミス、コスト過多
教材の価格設定は難しいものです。高すぎれば受講者が集まらず、逆に安すぎると収益が出にくいだけでなく、質の低い受講者が集まりやすいという問題もあります。さらに、制作に過剰なコストをかけてしまい、採算が取れなくなるケースも少なくありません。
このような失敗を避けるには、「学習者が得られる成果」を基準に価格を決めることが大切です。同じ分野の教材の相場を調査し、講師の実績、サポート内容、演習の充実度といった差別化ポイントを価格に反映させましょう。
また、最初から高額な機材や有料ツールに依存するのではなく、まずは低コストで最小限の完成形を作り、受講者の反応を見ながら段階的に投資を拡大していくのが最適な方法でしょう。
5 一回限りの作成で、販売後に改善しない
「一度教材を作ったら終わり」と考えてしまうと、大きな失敗につながります。オンライン教材は作ったまま放置するのではなく、直したり追加したりしていくことで価値を保てます。
逆に更新しないと、内容が古くなってしまい、受講してくれる人やこれから利用する方からの信頼もなくなってしまいます。特に今の時代は、情報がすぐに古くなるので要注意です。
これを防ぐコツは「フィードバックをもらう仕組みを作ること」です。例えば、受講後にアンケートを取ったり、レビューを集めたりして、「わかりにくかったところ」や「もっと知りたい内容」を探します。
それをもとに直したり、新しい情報を追加したり、質問を教材に反映させれば、教材はどんどん良くなります。
差別化のポイント!ユニークな教材を作るためのコツ
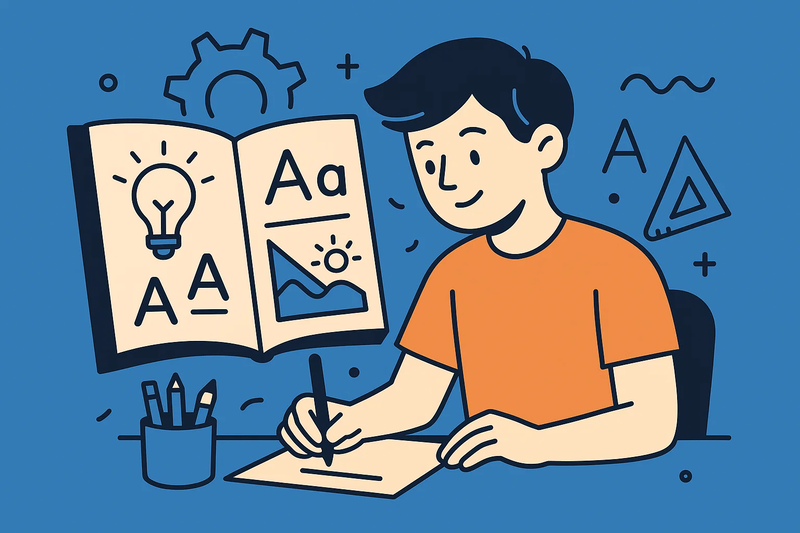
オンライン教材は年々どんどん増えています。そのため、よくある内容だと目立たずに埋もれてしまい、他と違う特別な教材にするためには工夫が必要です。
その一つが「ストーリーテリング」です。物語のように話を組み立てて、学ぶ人が「わかる!」とか「自分も同じ気持ちだ」と思える体験を盛り込むと、心に残りやすくなります。
また、クイズやワークシートを入れることで、ただ読むだけ・聞くだけではなく「自分から参加して学ぶ」意識を持てるようになります。
さらに、自分で作ったテンプレートや特別な資料を配れば、「ここでしか学べない」と感じてもらうことができます。
そして、教材のデザインやレイアウトをそろえることで「ブランドらしさ」が出て、学ぶ人は教材を通じて特別な体験を得ることができます。
こうした工夫が、ユニークで魅力ある教材を作るカギになります。
オンライン教材の将来性は高い
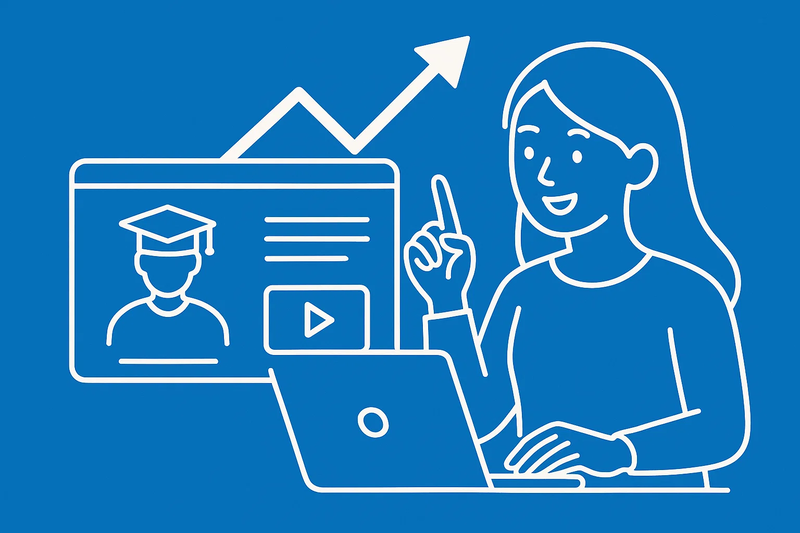
近年の学習環境の変化により、オンライン教材の需要は確実に拡大しています。リモートワークやDX推進に伴い、企業研修もオンライン化が進み、教育現場でもデジタル教材が標準化されつつある印象です。
さらに個人レベルでも、副業やスキルアップのために自宅で学べるオンライン教材のニーズは高まっています。
テクノロジーの進化により、AIによる学習サポートや自動フィードバック、VR・ARを活用した没入型教育など、新たな形の教材も登場するでしょう。
これらの流れから見ても、オンライン教材は一過性のブームではなく、学習の主要なスタイルとして今後さらに広がると考えられます。
教育者や企業にとっても大きなビジネスチャンスがある分野です。
オンライン教材を販売するならWisdomBase
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
自社オリジナルのオンライン教材を届けたい。そんな思いを持つ企業や教育機関の皆さまに、私たちが提供しているのが eラーニングシステム WisdomBase です。
受講申し込みから学習の進捗・成績管理、修了証の発行までをすべてオンラインで完結できるため、運営にかかる手間を大幅に軽減できます。
さらに、リスキリングや昇進試験、検定対策、リカレント教育など、幅広いシーンに柔軟に対応できる設計となっており、人材育成のあらゆる課題解決を強力にサポート。
DX時代の人材育成に不可欠な基盤として、WisdomBaseは学びの場を進化させ、組織の成長を後押しします。オンライン教材の販売や運営を検討されている方は、ぜひWisdomBaseを活用ください。 wisdombase.share-wis.com
まとめ
オンライン教材は、正しい手順で計画・制作・販売を進めれば、学習者にとっても提供者にとっても大きな成果を生み出す仕組みになります。
動画やテキスト、音声といった形式を適切に組み合わせ、フィードバックや更新を繰り返すことで、学習効果の高い教材を提供できるでしょう。さらに、価格設定や販売戦略を工夫すれば、短期間で成果を出すことも可能です。
今後、オンライン教育はますます広がり、AIやVRを取り入れた新しい形の学びも登場するでしょう。こうした変化に対応するためには、単に教材を作るだけでなく、継続的に改善し、進化させていく姿勢が欠かせません。
オンライン教材の作成と運営は、教育現場だけでなく企業や個人にとっても大きなビジネスチャンスとなります。

