
はじめに
「昇格試験のケーススタディ、何を書けば評価されるんだろう…」
そんな不安を抱えていませんか?論文や筆記と違い、ケーススタディは模範解答が見えにくく、「自分の答えが正しいのか」判断が難しいのが特徴です。
この記事では、ケーススタディ試験の基本から出題例、模範解答、評価ポイント、そして合格に向けた準備のコツまでを紹介します。実際の出題イメージを押さえることで、自信を持って試験に臨むためのヒントをつかんでいただけます。
- はじめに
- ケーススタディ試験とは?
- ケーススタディ試験で問われる力
- 出題例から学ぶ|昇格試験のケーススタディ例題
- 模範解答と解説
- 評価されるポイントとNG回答
- 昇格試験対策のコツ
- 昇格試験をオンライン化するならWisdomBase
- まとめ
ケーススタディ試験とは?
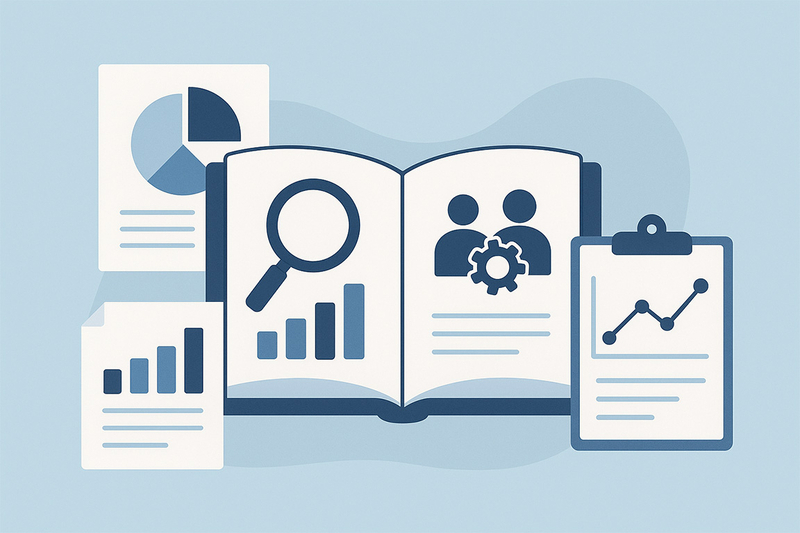
ケーススタディ試験とは、与えられた事例をもとに課題を見つけ出し、原因を分析し、解決策を考える力を測る試験形式です。知識を暗記して答える筆記試験とは違い、実際の業務に近い状況設定がされるのが特徴です。
昇格・昇進試験でこの形式が用いられるのは、管理職として必要な
- 状況を把握する力
- 問題を整理する力
- 現実的な解決策を導く力
を確認するためです。単に正しい答えを出すことよりも、考え方のプロセスや、組織全体を見渡した視点が重視されます。
たとえば「部下が目標を達成できなかった」「顧客からクレームが入った」など、職場で実際に起こりうるシナリオが題材になります。
つまり、ケーススタディ試験は単なる試験問題ではなく、「管理職としてどう行動できるか」を問う実践的な評価手段なのです。
ケーススタディの一般的な出題形式
ケーススタディ試験では、実際の業務を想定したシナリオが与えられ、その状況にどう対応するかを論理的にまとめることが求められます。
どの形式であっても、問われているのは「課題を見つけ、分析し、現実的な解決策を示せるか」という点です。普段の業務経験をベースに、論理的に整理して表現できるかどうかが合否の分かれ目となります。
形式はいくつかありますが、代表的なのは次の3つです。
論述型(小論文形式)
与えられた事例を読んで、自分の考えを文章にまとめる形式です。序論・本論・結論の流れを意識し、課題の把握から解決策までを一貫して説明する必要があります。
設問回答型
シナリオに対して「問題点は何か?」「原因は何か?」「どんな対応策を取るべきか?」といった設問が分かれて提示されます。設問ごとに簡潔かつ筋の通った答えを書くのがポイントです。
グループ討議型
複数人で与えられた課題について話し合い、合意形成を目指す形式です。論理力に加えて、リーダーシップや協調性、コミュニケーション力も評価されます。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
ケーススタディ試験で問われる力

ケーススタディ試験は「正解を書けるか」ではなく、「課題をどう整理し、どんな筋道で答えにたどり着くか」を見る試験です。評価の中心になるのは次の4つです。
問題発見力:理想と現実のギャップをとらえる
最初のつまずきやすいポイントが「問題設定」です。
問題とは、単なる出来事ではなく 「目標やあるべき姿」と「現状」との差=ギャップ です。
- 例:「売上目標100に対して実績80(20のギャップ)」
- 例:「“品質第一”を掲げているのに、初期不良率が許容基準を超えている」
ここで原因を深掘りするのはまだ早い段階。まずは「どんな差があるのか」を一文で定義できるかどうかが評価されます。
原因分析力:ギャップが生じた要因を整理する
次に、その差がなぜ生じたのかを分析します。表面的な言い訳や単一要因で片付けるのではなく、複数の視点から整理 するのがポイントです。
- 人:リーダーの役割不明確、教育不足
- プロセス:進捗管理が形骸化、KPI未設定
- 仕組み:商品や販促の戦略不在、ルール不徹底
- 外部:市場縮小、競合の攻勢、原材料高騰
「なぜ?」を繰り返し、本質的な原因を特定できれば、次の打ち手に説得力が生まれます。
解決策立案力:実行可能で優先度のある打ち手を示す
施策は理想論ではなく 「現場で本当に実行できる計画」 であることが重要です。
さらに、短期と中期で分け、誰が・いつまでに・どう測るか を明記すると評価が上がります。
- 短期策:重要顧客への即時対応(責任者・期限を明示)
- 中期策:市場調査や仕組み改善を計画化し、効果指標を設定
抽象的に「改善する」「連携を強める」と書くより、行動がイメージできるレベル で示すことが合格答案の条件です。
マネジメント力:人と組織を動かす視点を加える
最後に問われるのは、管理職候補らしい「人を巻き込み、組織全体で解決する力」です。
- 合意形成:上司・他部門との調整、説明責任
- 部下育成:OJTや研修を通じたスキル強化
再発防止:標準化・仕組み化で継続的に改善
「自分ならこうやる」で終わらず、チームで成果を出し続けられる仕組み まで描けると、評価者の目に管理職らしさが映ります。
出題例から学ぶ|昇格試験のケーススタディ例題

ケーススタディ試験では、受験者が「管理職としてどう考えるか」が試されます。ここでは例題を2つ紹介します。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
例題1:働き方改革に伴うシフト調整トラブル
あなたはサービス業の店舗マネージャーです。会社の方針で残業削減とワークライフバランス推進が打ち出され、勤務シフトの見直しが求められています。ところが、ベテラン社員からは「顧客対応に支障が出る」、若手社員からは「勤務時間が増えて負担が重い」と不満が出ています。
マネージャーとして、この状況をどう整理し、店舗運営を維持しながらチーム全体の納得感を得るかを論じなさい。
例題2:プロジェクトの納期遅延とメンバー離職の危機
あなたはシステム開発部の課長です。大型案件を進めるチームで、納期が迫る中、主要メンバーの1人が「過重労働で体調不良のため退職を考えている」と相談してきました。プロジェクトはこのメンバーの知識に大きく依存しており、退職となれば納期にも影響が出る可能性があります。
課長として、この状況をどう受け止め、顧客への責任とメンバーの健康・モチベーションの両立をどのように図るかを記述しなさい。
模範解答と解説

ケーススタディ試験の準備では、実際の答案イメージを知っておくことが非常に有効です。ここでは、先ほど紹介した2つの例題について、模範的な解答を本文形式でまとめ、その要約と解説も添えました。
例題1:働き方改革に伴うシフト調整トラブル
模範解答(本文:約560字)
私は店舗マネージャーとして、まず「残業削減の会社方針」と「顧客サービス維持」の間にギャップがあることを問題と捉える。現場ではベテラン社員が顧客対応低下を懸念し、若手社員は勤務負担の増加に不満を抱いており、チーム全体に不安が広がっている。
原因は三つある。第一に、繁忙時間帯の分析が十分でなく、シフトが経験則に頼って決められていること。第二に、ベテランのノウハウが若手に引き継がれておらず、仕事の負担が偏っていること。第三に、働き方改革の目的や意義がきちんと共有されず、「現場の犠牲」と受け止められていることである。
これを踏まえて、短期的には来店データを活用し、繁忙時間に合わせて人員を重点配置する。また、ベテランと若手のペア勤務を増やし、OJTを通じて知識や接客スキルを伝承する。同時に、方針説明会を開き、会社がなぜ残業削減を重視するのかを明確に伝え、従業員が意見を出せる場を整える。
中期的には、接客マニュアルやチェックリストを整備し、業務を標準化する。ベテランは教育役として活躍でき、若手は成長を実感できる仕組みにすることで、不満の解消と意欲向上を図る。
私はこの取り組みを通じて、店舗運営と働き方改革を両立させたい。単なるシフト調整にとどまらず、チーム全体の成長と働きやすさを実現することが、マネージャーとしての責任である。
模範解答(要約)
- 問題:会社方針と現場のサービス維持の間にギャップがある。
- 原因:①シフト設計にデータ不足、②ノウハウ未共有、③方針の意義が伝わっていない。
- 解決策:短期=データ活用シフト・OJT・説明会、中期=業務標準化・教育役割付与。
- 管理職視点:現場の声を吸い上げつつ方針を浸透させ、働きやすさと成長を両立させる。
解説
この解答は「問題=ギャップ」という基本を明確に示し、原因を3点に整理しています。短期と中期の施策を分けた点も論理的で評価されやすいポイントです。また、単に効率化に留まらず「ベテラン育成役/若手成長機会」というマネジメントの視点を加えているため、管理職候補としての姿勢が伝わります。
NGになりやすいのは「人員を増やす」といった非現実的な提案や、「頑張る」「協力する」など抽象的な表現だけで終わる解答です。実行可能な施策と人材育成の視点を盛り込むことが合格答案のカギになります。
例題2:プロジェクトの納期遅延とメンバー離職の危機
模範解答(本文:約560字)
私は課長として、まず「顧客への納期責任」と「メンバーの健康維持」の間にギャップがあることを問題と捉える。業務が特定の社員に集中しすぎた結果、体調不良による離職リスクが顕在化し、プロジェクト全体が不安定な状態にある。
原因は三点に整理できる。第一に、主要工程の知識やノウハウが属人化し、特定メンバーへの依存が強いこと。第二に、進捗や負荷をマネジメントが十分に把握できず、業務調整が後手に回ったこと。第三に、私自身を含め、チーム全体で「働き方の持続可能性」を意識した運営ができていなかったことである。
対応として、短期的にはまず当該メンバーの業務量を調整し、体調回復を優先する。残タスクは他のメンバーへ分担し、必要に応じて外部リソースの一時投入を検討する。同時に、顧客に現状を率直に説明し、リスクを共有したうえでスケジュール調整や追加支援を交渉する。
中期的にはナレッジ共有の仕組みを整備する。重要工程を手順書化し、コードレビューやペア作業を導入することで、知識をチーム全体に広げる。さらに、定期的な1on1を行い、負荷や体調のサインを早期に把握できるようにする。
私はこの一連の取り組みを通じて、納期を守る責任と同時に、チームの持続可能な働き方を実現したい。人を守りながら成果を出す姿勢こそ、管理職として最も大切な役割であると考える。
模範解答(要約)
- 問題:納期責任とメンバー健康維持の間にギャップがある。
- 原因:①属人化、②進捗把握の不十分、③持続可能性への意識不足。
- 解決策:短期=業務量調整・タスク分担・外部支援・顧客説明、中期=手順書化・レビュー導入・1on1強化。
- 管理職視点:成果と健康の両立を図り、チームが継続的に成果を出せる体制を築く。
解説
この解答は「ギャップ→原因→短期施策→中期施策→マネジメント視点」という流れをしっかり踏んでいます。特に「顧客への説明」「外部リソース検討」「1on1による早期把握」など、具体的で現実的な行動が示されている点が評価されます。
評価者が注目するのは「人を守りつつ成果を出すバランス感覚」です。個人に依存しない仕組みづくりまで言及できれば、管理職候補としての視座が伝わります。逆に、短期の火消しだけで終わる答案や、「頑張る」といった抽象的な表現は減点につながります。
評価されるポイントとNG回答

ケーススタディ試験では、「何を答えたか」以上に「どう考え、どう表現したか」が重視されます。評価者は答案を通じて、管理職としての視点や論理性を見極めています。ここでは代表的な評価ポイントと、注意すべきNG回答の特徴を整理します。
評価されるポイント
- 論理の一貫性:問題発見 → 原因分析 → 解決策 → マネジメント視点の流れが崩れていないか。筋道が明確だと、多少の表現不足があっても評価されやすくなります。
- 立場に即した視点:「課長として」「マネージャーとして」といった役割を意識しているか。自分一人での対応ではなく、部下や他部署を巻き込む視点があると管理職らしさが伝わります。
- 具体性と実現可能性:「改善する」「連携を強める」といった抽象的な言葉だけでなく、誰が・いつ・どのように行うのかを示せているか。実際に動ける施策として書かれていることが重要です。
- 組織全体への配慮:短期的な成果だけでなく、人材育成や再発防止など、持続的に効果を生む視点があるか。組織全体を見渡す姿勢が高く評価されます。
NG回答の特徴
- 表面的な答えに終始する:「顧客に謝罪する」「会議を開く」など、誰でも思いつく行動だけで終わる答案は評価が伸びません。
- 責任転嫁や他責志向:「部下が悪い」「他部署の協力不足」など、原因を他人に押し付ける表現は大きな減点要素です。
- 抽象的・スローガン的な表現:「一丸となって頑張る」「意識を高める」など、実行の中身が伴わない言葉は説得力を欠きます。
- 役割意識の欠如:管理職候補としての立場を忘れ、自分一人の行動だけを記述すると「視野が狭い」と評価されがちです。
昇格試験対策のコツ

ケーススタディ試験は、知識量だけでなく「考えをどう整理し、どう伝えるか」が問われます。ここでは準備の際に押さえておきたい実践的なコツを紹介します。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
限られた時間で答案をまとめる練習をする
試験本番は制限時間が60〜90分程度と限られています。普段から「設問を読む→問題を定義→原因を整理→解決策を箇条書き→文章化」という流れを時間を区切って練習しておくと、当日慌てずに済みます。
フレームワークを活用して論理を整理する
「問題=理想と現実のギャップ」「原因=人・組織・仕組み・外部」「解決策=短期と中期」といった枠組みを持っておくと、答案の型が安定します。フレームワークは型にはめすぎる必要はありませんが、思考の抜け漏れを防ぐ効果があります。
自分の経験を答案に活かす
管理職経験がなくても、「後輩を指導した」「部署間の調整をした」など日常の業務経験は必ずあるはずです。それらを具体例として盛り込むことで、説得力が増し、自分の言葉で書ける答案になります。
模範解答を“写経”して型をつかむ
実際の模範解答を手で書き写し、構成や表現を体感するのも効果的です。書き方のリズムや表現の幅を身につけることで、自分の答案にも自然と厚みが出てきます。
昇格試験をオンライン化するならWisdomBase
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
当社では、オンライン試験システム WisdomBase を提供しています。昇格試験をはじめとする社内試験のオンライン化をサポートし、企業が直面しがちな「不正防止」「運営効率化」といった課題を解決してきました。
WisdomBaseは、制限時間や出題形式の柔軟な設定、カメラ監督による不正対策、数百人規模の同時受験にも対応できる安定性を備えています。また、導入前の要件整理から当日の運用まで、担当者が伴走しながら支援するため、初めてオンライン試験に取り組む企業でも安心です。
実際に、全国規模で社員試験を実施している企業に導入いただき、従来の工数やコストを大幅に削減するとともに、公平性と透明性の高い試験運営を実現しています。
昇格試験のオンライン化にご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。
wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
まとめ
昇格試験のケーススタディは、正解を探す試験ではなく、管理職としての思考力や判断力を示す場です。
ポイントは次の流れを押さえることにあります。
- 問題発見:理想と現実のギャップを明確にする
- 原因分析:なぜそのギャップが生じたのかを整理する
- 解決策立案:実行可能で現実的な打ち手を提案する
- マネジメント力:部下育成や組織全体への視点を加える
実際の例題や模範解答を通じて、この流れを繰り返し練習すれば、答案に一貫性が生まれます。大切なのは、経験の有無ではなく「考えを筋道立てて表現できるか」です。
準備を進める中で、模範解答を写経したり、自分の業務経験を振り返って答案に落とし込む練習をすると、試験本番でも安心して臨めるでしょう。

