
はじめに
「職場での何気ない発言って、どこからがハラスメントになるの?」 「ハラスメントを防ぐために企業はどんな取り組みをしているの?」 「実際に効果があった成功事例を知りたい!」
といった疑問をお持ちの方に向けて、この記事では ハラスメント防止の基本的な考え方から、相談窓口や研修、ガイドライン整備といった具体策、さらに実際に成果を上げた企業の成功事例 をわかりやすく紹介しています。
人事担当者や経営層の方はもちろん、日々の働き方を見直したいビジネスパーソンにも役立つ内容です。ぜひ参考にしていただき、自社や職場でのハラスメント対策に活かしてみてください。
- はじめに
- ハラスメントとは
- ハラスメントをなくすための具体的な取り組み
- ガイドラインや就業規則の明記
- ハラスメントの加害者にならないためにできること
- 成功事例から学ぶハラスメント防止のポイント
- 【番外編】賛否両論の“無言のハラスメント対策”から学べること
- ハラスメント対策を進めるならWisdomBase
- まとめ
ハラスメントとは
 ハラスメントをなくすための最初のステップは、その意味や種類をしっかり理解することです。もし誤解やあいまいな認識のまま放置してしまうと、知らないうちに加害者や被害者のどちらにとっても不利益につながってしまいます。
ハラスメントをなくすための最初のステップは、その意味や種類をしっかり理解することです。もし誤解やあいまいな認識のまま放置してしまうと、知らないうちに加害者や被害者のどちらにとっても不利益につながってしまいます。
厚生労働省のガイドラインでは、ハラスメントは「相手の尊厳を傷つける言動」とされており、代表的なものにはパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどがあります。
特に職場ではパワハラが起きやすく、指導との線引きがあいまいになってしまうことが大きな課題です。
もしハラスメントをそのままにしてしまうと、社員の心の不調や離職の増加、さらには企業全体の信頼が損なわれるなど、大きな影響を及ぼします。そのため、企業にとっても「リスクを防ぐ大切な取り組み」として、早めに対策を進めることが欠かせません。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
ハラスメントをなくすための具体的な取り組み
 ハラスメントをなくすためには、組織としての仕組みづくりと、社員一人ひとりの意識改革の両方が欠かせません。
ハラスメントをなくすためには、組織としての仕組みづくりと、社員一人ひとりの意識改革の両方が欠かせません。
人事担当者や経営層が実践できる施策は数多くありますが、特に効果的なものを段階的に取り入れることで、持続的に成果を上げることができます。 ここでは、実効性の高い代表的な取り組みをステップごとに紹介します。
相談窓口の設置と周知徹底
まず基本となるのが、社員が安心して声を上げられる相談窓口の設置です。どんなに優れた制度やルールを用意しても、社員が「相談しても大丈夫だ」と思えなければ機能しません。
そのため、相談窓口を社内に設置するだけでなく、外部の専門機関と連携することも効果的です。
外部の窓口があれば、利害関係に左右されない公平な対応が可能となり、被害を受けた社員も安心して利用できるでしょう。さらに、窓口の存在を社内報や研修、ポスターなどを通じて周知徹底することも欠かせません。
ハラスメント研修の実施
次に大切なのが、ハラスメントに関する研修です。加害者となってしまう人の多くは「自分がそんなつもりではなかった」と振り返るケースが少なくありません。
つまり、無意識の言動が相手を傷つけている場合が多いのです。研修では「どんな行為がハラスメントに当たるのか」を具体的な事例を交えて伝えることで、社員の理解が深まります。
特に管理職向けには、指導とパワハラの違いを丁寧に解説することが大切です。これにより、指導の仕方を改善しつつ、部下との信頼関係を築けるようになります。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
ガイドラインや就業規則の明記
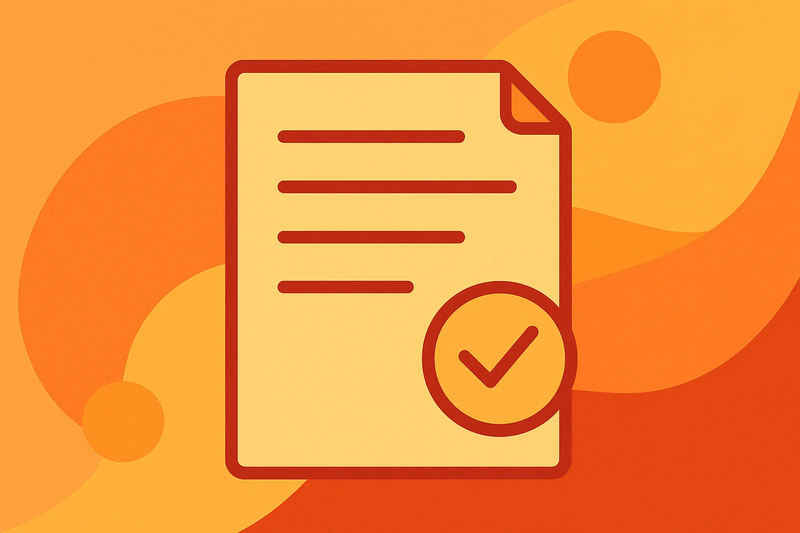 ハラスメント防止には、ルールの明確化も必要です。就業規則やガイドラインに、ハラスメント行為の定義や禁止事項、そして違反した場合の懲戒規定をはっきりと記載することで、社員全員が共通認識を持てます。
ハラスメント防止には、ルールの明確化も必要です。就業規則やガイドラインに、ハラスメント行為の定義や禁止事項、そして違反した場合の懲戒規定をはっきりと記載することで、社員全員が共通認識を持てます。
ルールがあいまいだと「これはセーフなのでは?」といった誤解が生まれやすく、結果的にトラブルの温床となってしまいます。曖昧さを排除し、誰もが理解できる形で周知することが、未然防止につながります。
証拠の収集と対応プロセスの明確化
実際にハラスメントが発生した場合に備えて、被害者が安心して行動できる環境を整えることも大切です。被害者には、録音やメール保存、日付入りのメモなど、できる限り証拠を残すことをおすすめします。
一方で企業側は、通報があった場合の流れを明確にしておくことが求められます。たとえば「通報 → 調査 → 判断 → 処分 → 再発防止策」というプロセスをあらかじめ決め、全社員に周知しておくと、公平性や透明性が担保されます。
このように対応プロセスを整えておくことで、被害者の心理的負担を減らし、組織への信頼も高めることができます。
ハラスメントの加害者にならないためにできること
 ハラスメントをなくす取り組みは、組織全体の仕組みや制度の整備によって進められるものですが、それだけでは十分ではありません。実際の職場で日々のやり取りを行うのは社員一人ひとりであり、各自の意識や行動が大きく影響します。
ハラスメントをなくす取り組みは、組織全体の仕組みや制度の整備によって進められるものですが、それだけでは十分ではありません。実際の職場で日々のやり取りを行うのは社員一人ひとりであり、各自の意識や行動が大きく影響します。
つまり「自分は絶対に加害者にはならない」と思い込むのではなく、「誰もが加害者になる可能性がある」という前提に立ち、自分の言動を振り返る姿勢が大切です。ここでは、加害者にならないために心がけたい3つのポイントを紹介します。
無意識の言動に注意する
「ちょっとした冗談のつもりだった」「昔は普通に言われていた」。こうした言葉が、今の社会ではハラスメントとして捉えられることがあります。特に上下関係のある場面では、冗談が相手にとって大きなプレッシャーや不快感につながることも少なくありません。
大切なのは、自分の意図ではなく、相手がどう受け取るかという視点を持つことです。自分では軽く言ったつもりでも、相手が傷つけばハラスメントにあたる可能性があると意識しましょう。
「この一言は相手を尊重しているか」「立場が逆ならどう感じるか」と立ち止まって考える習慣が、予防につながります。
フィードバックの伝え方を工夫する
部下や後輩に注意や指導をする場面は、多くの職場で避けられません。その際、重要なのは「人格」ではなく「行動」に焦点を当てて伝えることです。
たとえば、「お前はダメだな」という言葉は相手の存在そのものを否定してしまいますが、「なぜ遅れたのか説明してほしい」という言い方であれば、具体的な行動に着目しています。
前者は相手のモチベーションを大きく損ねる可能性があるのに対し、後者は改善につながる前向きな対話を生み出せます。伝え方ひとつで相手の受け取り方は大きく変わるため、「相手の成長を支援する」という姿勢を常に持ち続けることが大切です。
多様性を尊重する
現代の職場では、性別や年齢、国籍、ライフスタイルなど、多様な背景を持つ人々が共に働いています。この違いを尊重する姿勢は、ハラスメント防止に直結するだけでなく、組織全体の活性化にもつながります。
例えば、世代間で価値観が違うことは自然なことですが、それを「非常識だ」と決めつけるのではなく、「そういう考え方もあるのか」と受け入れる姿勢が大切です。
また、家庭の事情やライフスタイルに配慮することも、信頼関係を築く大きな一歩になります。多様性を尊重できる職場は、安心して意見を言える心理的安全性が高まり、結果として組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。
成功事例から学ぶハラスメント防止のポイント
 近年、ハラスメントは企業経営における大きなリスクとして注目されています。厚生労働省の指針でも、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどを防ぐ取り組みは「リスクマネジメントの一環」と位置づけられ、すべての事業者に対応が求められています。
近年、ハラスメントは企業経営における大きなリスクとして注目されています。厚生労働省の指針でも、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどを防ぐ取り組みは「リスクマネジメントの一環」と位置づけられ、すべての事業者に対応が求められています。
ハラスメントを放置すると、社員のメンタル不調や離職率の上昇、法的トラブルの発生、さらには企業の社会的信用の低下といった深刻な影響を招きます。そのため、多くの企業が独自の防止策を導入し、実際に成果を上げています。
こうした成功事例を学ぶことは、他の企業にとっても自社の取り組みを考えるうえで非常に参考になります。 以下では、代表的な成功事例を3つ取り上げ、その効果と学ぶべきポイントを紹介します。
ケース1:定期研修で再発率を大幅に低下
ある大手企業では、全従業員を対象にしたハラスメント防止研修を年1回の必須プログラムとして導入しました。さらに特徴的なのは、新任管理職を対象とした特別研修を設けた点です。
管理職には部下を指導する立場がある一方で、その言動がパワーハラスメントと誤解されやすいリスクもあります。そこで、指導とハラスメントの境界線を正しく理解できるよう、具体的な事例やロールプレイを交えた実践的な学習を行いました。
この取り組みを継続的に実施した結果、研修後には管理職の意識が変化し、「指導の仕方に気を配るようになった」「部下とのコミュニケーションが改善した」といった声が多く寄せられました。
その成果として、社内で報告されるパワーハラスメントの再発率が大幅に減少し、職場全体の風通しも改善しました。 この事例からは、教育の継続性と管理職への重点的なサポートが効果的であることが分かります。
ケース2:匿名相談窓口で通報件数が増加
別の企業では、既存の相談窓口に加えて「匿名で利用できる通報システム」を導入しました。従来の窓口では「報復が怖い」「相手に知られるのが不安」といった理由から声を上げられない社員も多くいましたが、匿名性を担保することで心理的なハードルが下がり、実際に通報件数が増加しました。
一見すると「件数が増えた=問題が悪化している」と捉えられがちですが、実際には逆で、問題が表に出るようになったことで早期発見・早期対応が可能となりました。これにより、小さなトラブルの段階で解決でき、深刻化や長期化を防ぐことができたのです。
また、匿名相談窓口の存在は、社員に対して「会社は真剣に取り組んでいる」という安心感を与え、組織全体の信頼感向上にもつながりました。 この事例から学べるのは、相談体制の多様化が通報のしやすさを生み、結果として透明性の高い職場づくりにつながるという点です。
ケース3:ガイドラインの公開で企業イメージを向上
さらに、ある企業では社内ルールの整備だけでなく、ハラスメント防止方針や対応策を「ガイドライン」として社外に公開しました。
これは一見すると自社の弱点を外に示すように思われがちですが、実際には「この企業は職場環境改善に本気で取り組んでいる」というメッセージとなり、求職者や顧客にポジティブな印象を与えました。
特に採用活動においては「安心して働ける企業」として評価が高まり、優秀な人材を確保する上で有利に働きました。
また、社内においても公開したガイドラインに基づき、従業員一人ひとりがルールを意識するようになり、企業全体のガバナンス強化に寄与しました。 この事例からは、情報公開が内外の信頼醸成につながり、企業ブランドの価値向上にも直結することが明らかです。
【番外編】賛否両論の“無言のハラスメント対策”から学べること
 ハラスメント対策として、一部の企業では被害者を守るために「組織全体での無言の圧力」を行使した例もあります。
ハラスメント対策として、一部の企業では被害者を守るために「組織全体での無言の圧力」を行使した例もあります。
具体的には、ハラスメント行為を繰り返す上司に対し、同僚や部下、さらには他部署の社員までもが冷たい態度を取り、会話を必要最低限に制限。業務以外の場面で素っ気なく接し、飲み会や雑談にも一切誘わないといった徹底した「無視」の姿勢を共有しました。
その結果、加害者は徐々に孤立し、最終的には居づらくなって退職を選ばざるを得なくなったのです。もちろん推奨される対策ではありませんが、「組織が加害者を容認しない」という強いメッセージを示す点では一定の効果を発揮した事例といえるでしょう。
ハラスメント対策を進めるならWisdomBase
ノーマルタイプ
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
コンプライアンス研修をより効率的に進めたい企業には、法人向けLMS(学習管理システム)「WisdomBase(ウィズダムベース)」の導入がおすすめです。 WisdomBaseは、動画・テキスト・クイズ・アンケートといったさまざまな教材をまとめて管理でき、受講者一人ひとりの進捗状況や理解度をクラウド上で見える化できる学習プラットフォームです。
特にコンプライアンス分野の研修においては、次のような課題解決に役立ちます。 受講状況をリアルタイムで把握し、未受講者へは自動でリマインド通知
ハラスメント対策や情報セキュリティなどの教材を繰り返し視聴可能
クイズや確認テストで理解度をチェックし、“形だけの研修”を防止
法改正や不祥事発生に応じて教材をすぐに配信・更新できる柔軟性
さらに、動画のスキップ防止機能や受講履歴のエビデンス管理にも対応しており、安心して活用できる点も強みです。 「社内にコンプライアンス意識をしっかり根づかせたい」と考えている研修ご担当者様は、ぜひWisdomBaseを活用した運用を検討してみてください。
wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
まとめ
ハラスメント防止は、一度ルールや制度を整えただけで終わるものではなく、継続的に取り組む姿勢が求められます。
相談窓口の整備や定期的な研修、ガイドラインの明記や情報公開といった施策は、いずれも社員が安心して働ける職場づくりにつながります。
また、個人の意識改革も欠かせず、無意識の言動やフィードバックの仕方、多様性を尊重する姿勢が加害者にならないための重要なポイントとなるでしょう。
さらに、実際の成功事例から学ぶことで、自社の課題に合わせた施策を検討しやすくなります。企業が積極的にハラスメント対策に取り組むことは、社員の心理的安全性を高め、組織の信頼性や競争力を向上させる大きな一歩です。

