
はじめに
「社内研修だけでは十分に対応できていないのではないか」
そんな課題を抱える人事・人材開発担当者は少なくありません。専門性の高いスキルや最新の知見を効率的に取り入れる手段として、外部研修を導入する企業は増えています。
一方で、費用や自社への適合性といった懸念もあるため、導入にあたってはメリット・デメリットを正しく理解し、効果を最大化する工夫が必要です。
本記事では、外部研修の概要から種類、費用相場、選び方、効果を高めるポイントまでを整理して解説します。
- はじめに
- 外部研修とは?社内研修との違いを解説
- 社内研修と外部研修の比較表
- 外部研修の形式・種類
- 外部研修のメリット
- 外部研修のデメリットと注意点
- 外部研修にかかる費用の相場
- 外部研修で人気のテーマ・おすすめの研修内容
- 自社に合った外部研修サービスの選び方
- 外部研修の効果を最大化するためのポイント
- 自社オリジナルのeラーニング環境を構築するならWisdomBase
- まとめ
外部研修とは?社内研修との違いを解説

外部研修とは、研修会社や外部講師など社外の専門機関に委託して実施する研修のことを指します。開催場所は必ずしも社外とは限らず、自社に講師を招いて実施する場合や、オンラインで提供される場合も含まれます。つまり「外部の専門家が関与するかどうか」が、外部研修か否かを分けるポイントです。
社内研修とは?
一方、社内研修は自社の人材が講師を務め、企画から運営までを自社で完結する形態を指します。自社の方針や文化を反映しやすく、コストも比較的抑えられる反面、担当者や講師の負担が大きくなりやすいという特徴があります。
外部研修が注目されている理由は?
外部研修が注目されている背景には、ビジネス環境の変化スピードの加速があります。デジタル化やグローバル化に伴い、新しいスキルを迅速に取り入れる必要性が高まっているからです。
社内研修だけでは限界があり、外部の知見を活用して効率的に人材育成を行うことが、戦略的な人事施策の一環として重要視されつつあります。
社内研修と外部研修の比較表
外部研修を導入するかどうかを検討する際に役立つのが、社内研修との比較です。両者はどちらが優れているというよりも、目的や状況に応じて適切に使い分けることが重要です。以下の表で、主な違いを整理してみましょう。
| 項目 | 社内研修 | 外部研修 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 自社の人材(人事・管理職・経営層など) | 外部講師・研修会社 |
| コスト | 講師費用は不要だが、企画・運営に大きな工数がかかる | 受講費や講師料が発生。ただし内製の負担は軽減 |
| 内容の柔軟性 | 自社の方針や事業内容に合わせやすい | 基本は汎用プログラムだが、カスタマイズも可能 |
| 専門知識 | 社内に蓄積された知識やノウハウに限定 | 最新トレンドや外部の専門知識を効率的に学べる |
| 効果測定 | 自社の評価基準に沿って実施しやすい | 研修会社のアセスメントや外部評価を活用可能 |
| 社員への刺激 | 慣れた環境で安心感がある | 社外講師や異業種交流による新鮮な刺激を得られる |
このように、社内研修は「自社に合わせやすい反面、リソース負担が大きい」のに対し、外部研修は「コストが発生するものの、新しい知見を効率的に取り入れられる」という特徴があります。
実際の人材開発計画では、両者を組み合わせることで相互の弱点を補完するケースが多く見られます。
外部研修の形式・種類

ひとくちに「外部研修」といっても、その形式はさまざまです。目的や受講対象者、実施環境によって選ぶべき形式が異なります。ここでは代表的な4つのタイプを紹介します。
公開型研修(複数社合同で実施)
公開型研修は、研修会社や団体が企画し、複数の企業から参加者を募って実施される形式です。日時や会場は主催者側が決定するため、参加者は決められた条件のもとで受講します。
異業種交流の機会が得られ、他社の考え方や事例に触れられるのが大きなメリットです。一方で、スケジュールの柔軟性が乏しく、自社の都合に合わせにくい点は注意が必要です。
カスタマイズ研修(自社向けに内容を調整)
カスタマイズ研修は、外部の研修会社や講師と打ち合わせを行い、自社の課題や目的に合わせて内容を設計する形式です。
管理職向けリーダーシップ研修や、自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を反映した新入社員研修など、オリジナルのプログラムを構築できます。高い効果が期待できる一方、企画に時間とコストがかかる点がデメリットです。
オンライン研修(ライブ配信・オンデマンド)
インターネット環境があれば全国どこからでも参加できるのがオンライン研修です。ライブ配信型はリアルタイムで講師や参加者と交流でき、オンデマンド型は録画コンテンツを好きな時間に視聴できます。
移動や会場費のコストを削減できる点が魅力ですが、双方向性に欠ける場合があり、受講者の集中力や参加姿勢に左右されやすい側面もあります。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
eラーニング(LMS活用・反転学習も可能)
eラーニングは、学習管理システム(LMS)に教材を登録し、受講者が個別に学ぶスタイルです。時間や場所に縛られず、自分のペースで学習を進められる点が特徴です。大人数を対象にした一斉教育や、シフト制の職場での教育に適しています。
近年では「反転学習」と呼ばれる、事前にeラーニングで学んだ上で集合研修でディスカッションを行う手法も広がっています。ただし、受講者によっては学習を続けるのが難しく、知識の定着に差が出ることもあります。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
外部研修のメリット

外部研修には、自社だけでは得られない学びや環境が数多くあります。ここでは代表的なメリットを整理して紹介します。
専門家による質の高い研修が受けられる
外部研修の大きな強みは、その分野に精通した専門家から直接学べる点です。
社内研修では人事部門や管理職が講師を務めるケースも多いですが、必ずしも各分野の専門知識に長けているとは限りません。
外部研修であれば、日頃から教育現場で研修を行っている講師や、実務経験豊富な外部コンサルタントから、最新の知識や実践的なノウハウを効率的に学ぶことができます。
自社にないノウハウや最新トレンドを習得できる
業界を問わず、技術革新や市場環境の変化は加速しています。自社だけの知見に頼っていると、変化に取り残されるリスクもあります。外部研修を活用することで、他社事例や最先端のスキルに触れられ、社員に新しい発想や視点をもたらすことができます。
特にDXやリスキリングといったテーマでは、外部の最新知識を取り入れることが成果を大きく左右します。
社員のモチベーション・刺激につながる
同じ社内メンバーで行う研修は安心感がある反面、緊張感や新鮮さに欠けることもあります。外部講師の存在や、公開型研修での異業種交流は、社員に適度な刺激を与え、学びに対する姿勢を前向きにする効果があります。
「他社の優秀な人材と学んでいる」という意識が、研修後の行動変容やスキル活用につながるケースも少なくありません。
研修担当者の工数や準備負担を削減できる
社内研修をすべて自前で準備しようとすると、企画・教材作成・講師調整など膨大な工数が発生します。
外部研修を導入すれば、カリキュラム設計や教材準備を外部に任せられるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。特に大企業では対象者が多いため、研修準備の省力化は全体コストの削減にもつながります。
外部研修のデメリットと注意点

外部研修には多くのメリットがある一方で、導入にあたっては留意すべきデメリットやリスクも存在します。ここでは代表的な注意点を整理します。
社内研修より費用がかかる
外部研修は、受講料や講師料が発生するため、社内研修に比べてコストが高くなりがちです。特に公開型研修では参加者1人あたりの費用が設定されているケースが多く、受講人数が増えるほど総額も膨らみます。
カスタマイズ研修では、研修内容の調整費用や講師との打ち合わせにかかる時間・コストも加わるため、予算をしっかりと確保しておく必要があります。
日程調整や参加枠に制約がある
公開型研修は主催者が日程や会場を決めるため、自社のスケジュールに完全に合わせることはできません。また、人気の研修はすぐに定員が埋まってしまい、希望通りに参加できないこともあります。
講師派遣型でも、外部講師のスケジュールに依存するため、直前での変更や調整が難しい点は理解しておく必要があります。
自社課題に合わない内容になるリスク
外部研修の多くは汎用的なプログラムとして設計されています。そのため、自社特有の課題や事業内容に必ずしもフィットしない場合があります。
例えば、業界特有の商習慣や自社の評価制度に関する教育は、標準プログラムでは十分にカバーできないことがあります。内容をカスタマイズできるかどうかを事前に確認し、自社ニーズに合わせる工夫が欠かせません。
効果測定が難しく「やりっぱなし」になりがち
研修そのものは実施できても、社員が学んだことをどの程度業務に活かしているのかを把握できなければ、投資対効果は見えにくいままです。特に外部研修では、外部講師に依存する部分が大きく、研修後のフォローアップや成果測定が不十分になりやすい傾向があります。
「参加して終わり」にしないためには、事前に評価指標を設定し、社内での実践につなげる仕組みを整えることが重要です。
外部研修にかかる費用の相場

外部研修を導入する際に最も気になるポイントのひとつが「費用」です。形式や内容によって大きく変動するため、あらかじめ相場を把握しておくことが重要です。
ここでは代表的な形式ごとの費用感を整理します。
公開型研修の費用
公開型研修は、研修会社が設定した会場に参加者を派遣する形式のため、1人あたりの料金で費用が決まります。一般的なビジネススキル研修であれば、1日あたり15,000円〜30,000円程度が相場です。
新入社員研修など長期プログラムでは、1人あたり数十万円にのぼるケースもあります。人数が増えると総額が大きくなるため、必要に応じて社内研修との組み合わせを検討するのが現実的です。
オンライン・eラーニングの費用
オンライン研修やeラーニングは、1人ごとにIDを発行する課金体系が主流です。費用は1人あたり月額5,000円〜20,000円程度が目安で、加えて初期設定費用として10万円〜20万円がかかることもあります。
受講できるコンテンツ数に制限がなく、複数のテーマを網羅できるため、コストパフォーマンスに優れています。特に大人数を対象とする大企業では、定額制プランを活用することで一人当たりの単価を下げることが可能です。
講師派遣型・カスタマイズ研修の費用イメージ
外部講師を自社に招いて行う場合や、自社向けに研修内容をカスタマイズする場合は、講師料が中心となります。相場は1日あたり20万円〜50万円程度で、研修内容の調整や事前打ち合わせに追加費用が発生することもあります。
大規模な管理職研修や専門性の高い研修では、数百万円規模の投資が必要になる場合もあるため、予算計画を立てる段階で想定しておくと安心です。
助成金の活用でコストを抑える方法
外部研修にかかる費用は決して小さくありませんが、人材開発支援助成金などの制度を活用することで、費用の一部を補填できる可能性があります。
特にリスキリングやDX関連の研修は政策的にも支援が厚く、助成金の対象となりやすい分野です。予算策定時には研修会社や社労士と連携し、助成金の利用可否を確認しておくことが賢明です。
【関連記事】
wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
外部研修で人気のテーマ・おすすめの研修内容

外部研修を導入する際には、「どのテーマを選ぶか」が効果を大きく左右します。ここでは階層別・テーマ別に人気の高い研修内容を整理しました。
新入社員向け(ビジネスマナー・コミュニケーション)
社会人としての基礎を身につける新入社員研修は、多くの企業が外部に委託しています。代表的な内容はビジネスマナー、コミュニケーションスキル、タイムマネジメントなどです。外部講師から実践的に学ぶことで、基礎を早期に定着させる効果があります。
中堅社員向け(OJT指導・リーダーシップ・モチベーション)
中堅社員には、自分の業務に加え部下の育成やチームマネジメントが求められます。そのためOJT指導者研修やリーダーシップ研修、モチベーション向上研修などが人気です。
特に、育成方法やチームを動かす力は社内だけでは学びにくいため、外部の専門プログラムを取り入れることで効果的にスキルを養えます。
管理職向け(マネジメント・コーチング・ハラスメント防止)
管理職研修は外部研修の代表的テーマのひとつです。目標管理や組織マネジメント、コーチング、チームビルディングなど幅広いスキルを学びます。
近年ではハラスメント防止研修の需要が特に高まっており、職場環境の改善やコンプライアンス強化の観点から導入が進んでいます。
最新ニーズ(DX・リスキリング・グローバル人材育成)
近年注目を集めているのが、デジタルスキルやDX関連研修です。AI・データ分析・クラウド活用など、今後の競争力強化に欠かせない領域を外部研修で学ぶ企業が増えています。
また、グローバル人材育成や語学研修もニーズが高く、多国籍化が進む大企業ほど重要性が増しています。さらに政府も推進する「リスキリング」研修は助成金の対象になりやすく、費用対効果の面でも導入が加速しています。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
自社に合った外部研修サービスの選び方
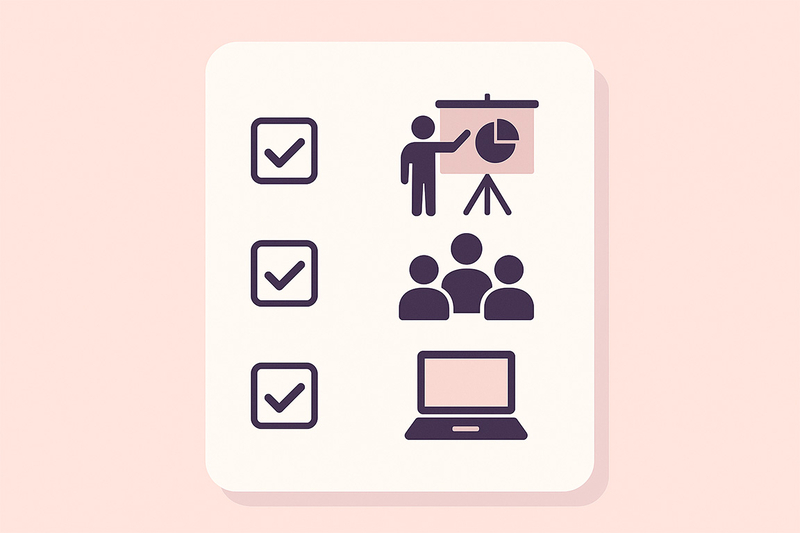
外部研修は提供会社やプログラムによって質や効果が大きく変わります。
単に費用や有名度だけで選ぶのではなく、自社の人材戦略に合致しているかどうかを見極めることが重要です。ここでは選定時に押さえておきたいポイントを紹介します。
研修会社・講師の実績や専門性を確認する
研修の成果は講師の力量に大きく左右されます。実施件数や対象企業の規模、業界実績などを確認し、信頼できるパートナーかどうかを見極めましょう。
また、講師が現役の実務家か教育専門家かによっても研修スタイルが異なります。自社のニーズに合ったタイプを選ぶことが大切です。
自社戦略・人材育成方針との整合性を見る
研修は単発で終わらせるのではなく、経営戦略や人材育成方針と連動してこそ効果を発揮します。
自社の中期的な人材開発の方向性と、外部研修が提供するカリキュラムが噛み合っているかをチェックしましょう。特に「次世代リーダー育成」や「DX推進」など、戦略テーマに直結する内容は投資効果が高まります。
カスタマイズ対応やアフターフォローの有無
外部研修の中には、汎用的なプログラムだけでなく、自社の状況に応じて内容を調整できるサービスもあります。
また、研修後に受講者の理解度を測定したり、フォローアップのセッションを提供したりする会社もあります。単発で終わらず、定着を支援してくれるかどうかは、成果に直結する重要なポイントです。
効果測定・アセスメント機能の提供状況
研修を実施しても、その効果が見えなければ投資対効果を説明できません。研修会社によっては、受講前後のアセスメントや行動変容を測る評価指標を提供してくれる場合があります。
定量的なデータをもとに社内で報告できる仕組みがあるかどうかも、サービス選定の大きな判断材料となります。
外部研修の効果を最大化するためのポイント

外部研修は実施するだけでは十分な成果が得られません。学んだ内容を業務に結び付け、長期的に活かすためには、事前準備から研修後のフォローまで一貫した仕組みが必要です。
ここでは効果を高めるための具体的なポイントを紹介します。
研修目的を明確にし参加者に共有する
研修を実施する理由が曖昧なままでは、受講者が「なぜ学ぶのか」を理解できず、効果が限定的になります。
経営戦略や人材育成方針と関連づけて、「この研修でどんなスキルを身につけ、どのように業務に活かすのか」を明示しましょう。目的を共有することで、受講者の主体性やモチベーションが高まります。
受講者の事前準備を徹底する
外部研修は限られた時間で多くの学びを得る場です。事前に配布資料や課題を共有しておくことで、当日の理解度が深まり、実践的な議論やワークに集中できます。
特に専門性の高いテーマでは、基礎知識を事前にインプットしてもらうことで研修効果が格段に高まります。
講師との事前打ち合わせで期待値を合わせる
研修会社や講師に丸投げすると、自社の課題と研修内容がずれてしまうことがあります。事前に求める成果や重点を伝え、可能であれば自社の事業内容や組織課題を共有しておくことが重要です。
講師との密な連携によって、自社に合った研修に仕上げることができます。
研修後のフォローアップ・実践機会を設ける
研修は受講直後が最も知識が定着しやすいタイミングです。学んだ内容を現場で試す機会や、社内で振り返りを行う仕組みをつくると効果が長続きします。
例えば、受講者による共有会やワークショップ、数か月後のフォローアップ研修を設けるのも有効です。
効果測定と振り返りで戦略的に活用する
「研修をやって終わり」にならないよう、効果測定は必須です。アンケートによる満足度調査に加え、知識定着度テストや行動変容の観察、業績への影響測定までを行うと、投資対効果が明確になります。
データに基づいて改善点を洗い出すことで、次回以降の研修をより戦略的に設計できるようになります。
自社オリジナルのeラーニング環境を構築するならWisdomBase
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
外部研修は専門知識を効率的に学ぶ有効な手段ですが、それだけでは自社特有の課題や日常業務に直結する教育まではカバーしきれないケースがあります。
最終的には、外部研修で得た知識を現場で活かすための「社内研修」や「継続的な教育施策」が欠かせません。
「WisdomBase(ウィズダムベース)」は、動画配信や試験機能を備えた国産のLMS(学習管理システム)です。社内で実施する研修やOJTを効率的に仕組み化し、受講履歴や習熟度を可視化することができます。
外部研修と社内研修を組み合わせることで、人材育成の効果は大きく高まります。社内研修の効率的な運用を検討される際には、ぜひ一度WisdomBaseをご検討いただければ幸いです。
wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
まとめ
外部研修は、社内にはない専門知識や最新のトレンドを効率的に取り入れられる有効な手段です。公開型研修やカスタマイズ研修、オンラインやeラーニングなど形式も多様で、自社の課題や目的に合わせて選択できます。
一方で、費用がかかることや、自社事情に合わない可能性、効果測定の難しさといったデメリットも存在します。そのため、社内研修と外部研修を上手に組み合わせ、自社戦略に沿った活用を行うことが重要です。
また、外部研修の成果を最大化するには、目的の明確化、受講者の事前準備、講師との打ち合わせ、研修後のフォローアップ、効果測定といった一連のプロセスを徹底することが欠かせません。これにより「やりっぱなし」ではなく、組織の成長につながる学びに変えることができます。
外部研修は単なる教育手段ではなく、人材育成を通じて経営戦略を実現するための重要な投資です。費用や手間だけに目を向けるのではなく、長期的な視点で組織にどのような成果をもたらすのかを見極めながら活用していきましょう。

