
はじめに
「マインドセットって結局どういう意味なの?」 「社員研修で“意識改革”って言われるけど、具体的に何をすればいいの?」 「マインドセット研修をやっても、現場で活かせていない気がする…」
そんなお悩みを持つ人事・教育担当者の方のために、今回は社員教育で成果を出すためのマインドセットの基本と実践法をわかりやすくまとめました。
「成長思考」「主体性」「失敗を学びに変える力」など、社員が前向きに行動するための考え方を、例文や研修設計のコツとあわせて紹介しています。
ぜひ参考にしていただき、研修や面談で社員の意識が変わる瞬間をつくってください。
- はじめに
- マインドセットとは?
- マインドセットが企業成長に与える影響
- 社員教育で伝えたい!マインドセットの使える例文
- マインドセットを定着させるための研修・面談での伝え方
- マインドセット教育を成果につなげるための設計ポイント
- よくあるマインドセットが失敗する理由
- よくある質問
- 社員のマインドセットの研修をするにはWisdomBase
- まとめ
マインドセットとは?

マインドセットとは、「物事の考え方」や「心の持ち方」を意味する言葉です。たとえば、同じ失敗をしても「もう無理だ」と思う人もいれば、「次はうまくやろう」と前向きに考える人もいます。
このような違いを生み出しているのがマインドセットです。ビジネスの現場においては、仕事の成果を左右するのは知識や技術だけでなく、考え方の方向性であるといわれています。マインドセットには大きく分けて2つのタイプがあります。
ひとつは「固定マインドセット」と呼ばれるもので、「自分の能力は生まれつき決まっている」と考える傾向があります。もうひとつは「成長マインドセット」で、「努力すればもっと伸びる」と信じる考え方です。
企業においては、この成長マインドセットを育てることが非常に重要です。なぜなら、社員が新しいことに挑戦し、失敗を恐れず改善に取り組むための土台となるからです。
人事や教育の担当者は、社員が前向きな姿勢で行動できるよう、このマインドセットを育成する研修や指導を行っています。
マインドセットが企業成長に与える影響

社員一人ひとりのマインドセットは、企業全体の成長や成果に大きな影響を与えます。たとえば、社員が「失敗しても学びに変えればよい」と考える職場では、新しいアイデアや挑戦が次々と生まれ、組織の活性化につながります。
反対に、「失敗したら責められる」と考える社員が多い職場では、守りの姿勢が強まり、変化に対応しづらくなる傾向があります。つまり、企業の成長は社員の考え方に大きく依存しているといえます。
近年では、マインドセットを重視する企業が増えており、研修や評価制度に「考え方の教育」を取り入れるケースも多く見られます。マインドセットの変化は目に見えにくいものの、組織文化や成果に影響を及ぼすでしょう。
そのため、スキル教育と並行して「どう考えるか」「どう行動するか」を育てる仕組みを整えることが、持続的な企業成長のためには欠かせません。
社員教育で伝えたい!マインドセットの使える例文
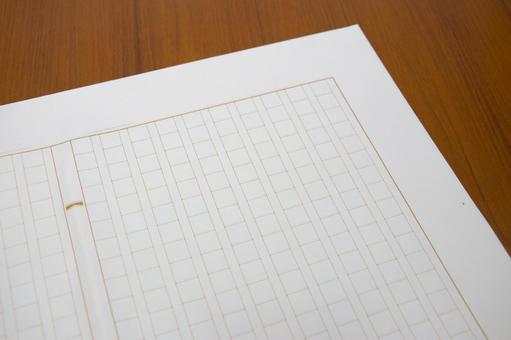
社員教育では、スキルや知識を教えるだけでなく、「どんな考え方で仕事に向き合うか」を伝えることも大切です。
マインドセットは、行動や判断のもとになる「考え方のクセ」のようなものです。詳細は以下の通りです。
- 成長思考を育むマインドセットの例文
- 主体性を引き出すマインドセットの例文
- 変化に強いマインドセットの例文
- チームワークを促すマインドセットの例文
- 失敗を成長に変えるマインドセットの例文
ここでは、社員研修や面談などで活用できる代表的なマインドセットと、実際に使える例文を紹介します。
成長思考を育むマインドセットの例文
成長思考とは、「今の自分はまだ途中であり、努力すれば必ず伸びる」と考える姿勢です。この考え方を持つ人は、新しいことに挑戦する意欲が高く失敗を恐れません。
例文: 「できないことがあるのは、成長のチャンスがあるということです。」 「完璧でなくていい。昨日より一歩進めば、それが成長です。」
このような言葉を使うことで、社員が「失敗を怖がるよりも学ぶことを楽しむ」気持ちを持てるようになります。
主体性を引き出すマインドセットの例文
主体性とは、「誰かに言われるから動く」のではなく、「自分で考えて行動する」姿勢のことです。主体的な社員が増えると、組織は自然と強くなります。
例文: 「誰かがやるのを待つより、まず自分が動いてみよう。」 「自分の仕事に責任を持てば、結果も自分でつくることができます。」
このようなメッセージは、社員が自分ごととして仕事に向き合うきっかけになります。
変化に強いマインドセットの例文
ビジネスの世界は常に変化しています。その変化を受け入れ、楽しむ姿勢が「変化に強いマインドセット」です。
例文: 「変化はチャンス。新しいことを学ぶチャンスでもあります。」 「慣れた方法にこだわるより、より良い方法を見つけていこう。」
この考え方を広めることで、社員は環境の変化に前向きに対応できるようになります。
チームワークを促すマインドセットの例文
チームで仕事を進めるうえでは、「自分だけが頑張る」ではなく、「仲間と力を合わせる」ことが大切です。
例文: 「チームの成功は、自分一人ではつくれません。みんなで作り上げるものです。」 「助け合うことで、できなかったことができるようになります。」 この言葉を伝えることで、社員の間に「信頼と協力」の文化が生まれます。
失敗を成長に変えるマインドセットの例文
仕事で失敗することは誰にでもあります。しかし、失敗をどう受け止めるかで、その後の成長スピードは大きく変わります。
例文: 「失敗はゴールではなく、学びのスタートです。」 「うまくいかなかった経験こそ、次の成功のヒントになります。」 このようなメッセージを研修で伝えることで、社員は失敗を恐れずに挑戦できるようになります。
マインドセットを定着させるための研修・面談での伝え方

マインドセットは、「考え方」や「物事の受け止め方」を表す言葉です。しかし、単に言葉で説明するだけでは、社員の心に深く届きにくいものです。
研修や面談の場では、社員が「なるほど、そういうことか」と納得できるように伝える工夫が大切です。つまり、頭で理解するだけでなく、以下の内容を心の中にしっかりと落とし込むことがポイントです。
- 社員が腹落ちする説明の順序
- 感情ではなく「行動レベル」に落とし込む話し方
- 評価面談や1on1で活かせる質問フレーズ例
ここでは、マインドセットを社員に定着させるための効果的な伝え方を3つの視点から紹介します。
社員が腹落ちする説明の順序
社員にマインドセットを伝える際は、最初に「なぜそれが大事なのか」という理由から話すことが大切です。
いきなり「成長マインドを持ちましょう」と言っても、社員は「どうして必要なのか」がわからず、行動に結びつきません。まずは背景を共有することで、聞き手の理解が深まります。
たとえば次のように話すと、社員に伝わりやすくなります。
「今の時代、変化がとても速くなっています。だからこそ、これまでのやり方にとらわれずに、新しいことを学び続ける姿勢が大切なんです。」 このように、状況の変化や会社の課題など共感できる現実から話を始めると、社員は自分ごととして受け止めやすくなります。
次に、「マインドセットを変えることでどんな良いことがあるか」を具体的に伝えます。たとえば、「考え方が変わると、上司とのやり取りがスムーズになる」「チームでの意見交換がしやすくなる」など、日常業務に関わる事例をあげると効果的です。
そして最後に、「具体的にどうすればよいか」という行動のヒントを伝えます。話の順序を「なぜ → どんな効果がある → どうすればいい」と整理することで、社員が自然に理解し、納得して行動につなげやすくなります。
感情ではなく「行動レベル」に落とし込む話し方
マインドセットを伝えるときに注意したいのは、「気持ちを変えよう」と感情に訴えすぎないことです。
「もっと前向きに」「意識を高く持とう」といった言葉だけでは、聞き手は一時的にやる気になっても、行動は長続きしません。大切なのは、どんな行動をすればいいのかを一緒に考えることです。
たとえば、「成長マインドを持とう」というテーマなら、次のように言い換えるとわかりやすくなるでしょう。
「一日ひとつ、新しいことを調べてみよう」 「できなかったことをノートに書いて、次にどうすればできるか考えてみよう」 このように、具体的な行動の形にすることで、社員は“気持ち”ではなく習慣としてマインドセットを身につけることができます。
研修や面談では、抽象的な言葉をそのまま使うのではなく、「それをやると、どんな行動が増えるのか」を一緒に整理して伝えることが効果的です。行動に落とし込まれたマインドセットは、時間が経っても忘れにくく自然と定着していきます。
評価面談や1on1で活かせる質問フレーズ例
面談の場では、上司が一方的に話すのではなく、社員自身に考えさせる質問をすることで、マインドセットが深く根づきます。質問によって「自分で気づく力」を引き出すことが、行動変化の第一歩です。
以下は、実際に評価面談や1on1で使える質問フレーズの例です。
成長思考を促す質問例 「この半年で、自分が一番成長したと思うことは何ですか?」 「うまくいかなかったことから、どんな学びがありましたか?」
主体性を高める質問例 「もし上司がいなくても、どうやってこの課題を進めますか?」 「次の目標を、自分だったらどう設定したいですか?」
変化対応を促す質問例 「最近の変化の中で、一番ワクワクしたことは何ですか?」 「新しいやり方に挑戦するとしたら、どんなことを試してみたいですか?」
チーム意識を育てる質問例 「チームの中で、自分がもっと貢献できそうなことは何ですか?」 「周りのメンバーの成長を助けるために、できることはありますか?」
このような質問を通じて、社員が自分の考えを整理し、自ら答えを見つけることができます。
面談の目的は「評価」だけではなく、「気づきを促すこと」です。質問によって考えを引き出し、行動に変える支援をすることで、マインドセットは確実に定着していきます。 【関連記事】:
階層別で見る「求められるマインドセット」の違い

マインドセットは、すべての社員にとって大切な考え方ですが、会社の中での立場や役割によって、求められる内容は少しずつ変わります。
新入社員には「学ぶ姿勢」、中堅社員には「責任と自立」、そして管理職には「チームを導く考え方」が求められます。
それぞれの立場でどんなマインドセットを意識すれば良いのかを整理しておくことで、社員一人ひとりが自分の役割を理解し、より良い行動につなげることができます。詳細はこちらです。
- 新入社員に求められるマインドセット
- 中堅社員・リーダーに求められるマインドセット
- 管理職・マネージャーに求められるマインドセット
- 階層ごとに使える言葉と例文の変化
ここでは、階層別に「求められるマインドセット」と、それを伝えるための言葉や例文を紹介します。
新入社員に求められるマインドセット
新入社員に一番大切なのは、「学ぶ姿勢」と「素直さ」です。社会人としての経験がまだ少ない時期は、完璧にできることよりも、吸収しようとする姿勢が重要です。
また、わからないことをそのままにせず、周囲に質問したり、失敗を恐れず挑戦する姿勢が成長を早めます。
例文: 「できないことを恥ずかしいと思わず、学ぶチャンスと捉えよう。」 「素直に吸収する姿勢が、成長への一番の近道です。」
このようなメッセージを伝えることで、新入社員が完璧さよりも成長を意識する考え方を持ちやすくなります。
中堅社員・リーダーに求められるマインドセット
中堅社員やリーダー層には、「自立」と「周囲への影響力」が求められます。自分の仕事をこなすだけでなく、後輩やチームメンバーを支える立場になるためです。また、課題に直面したときに“どうすれば解決できるか”を考える姿勢も必要になります。
例文: 「問題を見つけたら、誰かの指示を待つ前に、まず自分で考えてみよう。」 「リーダーは、チームの前で一番に挑戦する姿を見せる人です。」
この階層では、「責任を持つこと」や「模範を示すこと」がポイントです。行動一つひとつがチームに影響を与えるという意識を持つことで、組織全体が前向きな雰囲気になります。
管理職・マネージャーに求められるマインドセット
管理職やマネージャーには、「視野の広さ」と「人を育てる意識」が求められます。自分の業務だけでなく、チーム全体や会社全体の方向性を考え、社員の力を引き出すことが役割です。
大切なのは、部下に完璧を求めるのではなく、「成長のチャンスを与える」考え方を持つことです。
例文: 「失敗を責めるのではなく、そこから何を学べるかを一緒に考えよう。」 「チームがうまくいくかどうかは、メンバーを信じて任せられるかにかかっています。」
管理職自身が成長マインドセットを体現することで、部下の挑戦意欲を引き出し、チーム全体の雰囲気が前向きになります。
階層ごとに使える言葉と例文の変化
マインドセットを伝える際は、立場によって響く言葉が変わります。新入社員には“勇気づける言葉”が効果的であり、中堅社員には責任と判断力を促す言葉、管理職には信頼と育成を意識させる言葉が適しています。
たとえば、同じ「挑戦」というテーマでも、次のように言葉を使い分けるとより伝わりやすくなります。
例文の変化: 新入社員向け:「まずはやってみよう。失敗しても学びがある。」 中堅社員向け:「挑戦は、周りを動かす最初の一歩です。」 管理職向け:「部下が挑戦できる環境をつくるのがリーダーの役割です。」
このように、階層に合わせて言葉を調整することで、社員は自分の立場に合った形でマインドセットを理解できます。 また、研修や面談では「あなたの立場では、どんな考え方が必要だと思いますか?」と問いかけるのも効果的です。自分の言葉で考えさせることで、学びがより深くなります。
マインドセット教育を成果につなげるための設計ポイント

マインドセット教育は、ただ「考え方を教える」だけでは本当の効果を発揮しません。社員が実際に行動を変え、成果につなげてこそ意味があります。
多くの企業が意識改革を目的に研修を行っていますが、短期間で終わってしまい、現場に戻ると元に戻ってしまうケースも少なくありません。
ここでは、マインドセット教育を理解で終わらせず、行動につなげるため以下の3つの設計ポイントを紹介します。
- 「理解」だけで終わらせない行動化の仕組み
- 成功体験を積ませるフィードバック
- マインドセットが根づく組織の条件
「理解」だけで終わらせない行動化の仕組み
マインドセット研修では、社員が「わかった」と感じることよりも、「やってみよう」と思えることが大切です。多くの研修が失敗する理由は、知識を得るだけで、実際の行動につながらないからです。
たとえば、「挑戦することが大事です」と説明しても、何をどう変えればいいのかが明確でなければ、行動に移すのは難しいでしょう。
行動化を促すには、研修の中で「小さな実践」を取り入れることがおすすめです。たとえば、「明日から一つ、新しいことに挑戦してみましょう」「今日の学びを明日の仕事で一度使ってみましょう」といった具体的な課題を出します。
さらに、1週間後に振り返りの時間を設けて「やってみてどうだったか?」を話すことで、学びが定着します。理解で終わらせず、行動を促す仕組みをつくることが、マインドセット教育成功の第一歩です。
成功体験を積ませるフィードバック
マインドセットを定着させるには、社員が「できた」「変われた」と感じる小さな成功体験を積むことが重要です。人は成功体験を通して、「自分にもできる」という自信を持ち、前向きな行動を続けるようになります。
研修や面談では、失敗を指摘するよりも「良かった点」「努力した点」に焦点を当ててフィードバックを行いましょう。たとえば、「昨日よりスムーズに話せていましたね」「前より早く対応できるようになりましたね」といった言葉をかけることで、社員は自分の成長を実感できます。
また、本人が自分で気づくことも大切です。質問を使って「前と比べて、どんな変化を感じますか?」と尋ねると、自分の成長を自覚しやすくなります。成功体験と適切なフィードバックを積み重ねることが、行動変化を習慣化するカギになります。
マインドセットが根づく組織の条件
個人の意識を変えるだけでは、マインドセットは長続きしません。組織全体が「挑戦を歓迎する雰囲気」や「失敗を責めない文化」を持つことが大切です。上司やリーダーが率先して新しい考え方を実践することで、周囲にも良い影響が広がります。
また、制度や評価の仕組みも重要です。たとえば、挑戦したことを評価に加えたり、改善提案を歓迎する仕組みを作ったりすることで、社員が安心して行動できる環境が整います。
マインドセットが根づく組織とは、社員が「行動しても大丈夫」「失敗しても次につなげられる」と思える会社です。 上からの押しつけではなく、現場全体で考え方を共有できる環境を整えることが、本当の意味での定着につながります。 【関連記事】: wisdombase.share-wis.com
よくあるマインドセットが失敗する理由

マインドセット研修を行っても、思ったような成果が出ないことがあります。その多くは、内容や伝え方に問題があるのではなく、「伝わり方」と「実践の仕組み」に原因があります。ここでは、ありがちな失敗の3つのパターンを紹介します。
「スローガン化」してしまう
「挑戦しよう」「変化を恐れるな」といった言葉を掲げても、それが日常の行動に結びついていなければ意味がありません。いくら良い言葉でも、現場で使われず、会議室のスローガンで終わってしまうと、社員は「またお題目だけか」と感じてしまいます。
このような状態を防ぐには、スローガンを具体的な行動例とセットで伝えることが大切です。たとえば、「挑戦しよう」ではなく、「一人ひとつ、新しいアイデアを出してみよう」といった形で、すぐに動ける行動に変換しましょう。
「意識を変えろ」と伝えただけ
「意識を変えよう」という言葉だけでは、社員にとって何をすればよいのかが分かりません。気持ちは変えようと思っても、行動のイメージが湧かないため、結局は何も変わらないことが多いのです。
伝える側は、「意識」ではなく「行動」に焦点を当てましょう。たとえば、「次の会議では、必ず一つ意見を言ってみよう」「困っている人がいたら、声をかけてみよう」といった具体的な行動を提案することで、社員は自然と意識も変わっていきます。
社員が「自分ごと化」していない
マインドセットが定着しない最大の理由は、社員が「自分のこと」として受け止めていないことです。「会社が言っているから」「上司に言われたから」と感じてしまうと、行動に本気さが生まれません。
これを防ぐには、社員自身に考えさせることが大切です。たとえば、「あなたにとって“成長”とは何ですか?」「今の仕事でどんなことを変えたいですか?」と問いかけることで、自分の考えとして整理できます。
自分の言葉で答えたことは、他人に言われたことよりも強く記憶に残ります。研修や面談の中で「自分で考える時間」を作ることが、マインドセットを自分のものとして定着させる一番の近道です。
よくある質問

よくある質問を、以下にて3つ紹介します。
Q1:マインドセット研修をしても、現場で変化が見られないのはなぜ?
A: 多くの場合、「意識を変えよう」という抽象的な呼びかけだけで終わっていることが原因です。
マインドセットは気持ちではなく行動に落とし込んで初めて定着します。たとえば、「挑戦を大切にしよう」ではなく「1週間に1回、新しい提案をしてみよう」と具体的な行動を設定することで、社員の変化が目に見える形で現れます。行動を通じて得られる「小さな成功体験」が、自発的な意識改革を生み出します。
Q2:社員のマインドセットを変えるには、どんな伝え方が効果的ですか?
A: ポイントは「なぜそれが必要か」→「どんな良いことがあるか」→「具体的に何をすればいいか」の順で話すことです。いきなり「成長マインドを持て」と言っても、社員は腹落ちしません。まず背景(時代の変化・会社の課題)を共有し、次にメリットを示し、最後に実践方法を伝えることで、理解が行動につながります。感情ではなく、日常の行動習慣に変換して伝えることが重要です。
Q3:マインドセットを社内文化として根づかせるにはどうすればいい?
A: 個人の努力だけでは長続きしません。組織全体で「挑戦を歓迎する」「失敗を責めない」文化をつくることが必要です。上司やリーダーが率先して新しい考え方を実践し、挑戦した社員を評価する仕組みを整えることで、社員は安心して行動できるようになります。
「失敗は終わりではなく、次への学びの始まり」という意識を全員で共有することが、マインドセットを根づかせる第一歩です。こうした考え方を社内文化として浸透させるためには、継続的な研修が欠かせません。研修効果を高めるためにも、以下のようなツールの活用を検討してみましょう。
社員のマインドセットの研修をするにはWisdomBase
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
近年、多くの企業が研修や講習のオンライン化を進める中で、活用が広がっているのがのが WisdomBase(ウィズダムベース) です。 WisdomBaseは、法人向けに設計されたeラーニングおよびオンライン試験システムで、受講者管理から教材配信、テスト実施、進捗状況の確認、修了証の自動発行までを一括で行うことができます。
また、高いカスタマイズ性と充実したサポート体制を備え、「自社独自の研修」「資格取得講座」「法定講習」など、さまざまな教育目的に柔軟に対応可能です。 「研修のオンライン化で効率を上げたい」「受講のアーカイブ動画を残したい」といった課題をお持ちの方は、ぜひWisdomBaseの導入をご検討ください。
wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
まとめ
マインドセットは、社員一人ひとりの行動や成果を左右する見えない力です。単なる意識改革ではなく、「行動に落とし込む仕組み」と「成功体験を積ませる設計」が、定着のカギとなります。
また、上司やリーダーが率先して成長マインドを体現することで、組織全体が前向きに変化していきます。
スキル教育だけでなく、考え方の教育を取り入れることが、これからの企業成長には欠かせません。マインドセットを育てる研修を通して社員が自ら学び、挑戦し続ける文化をつくっていきましょう。
気になる方は、こちらXもフォローを! Tweets by ShareWis x.com

