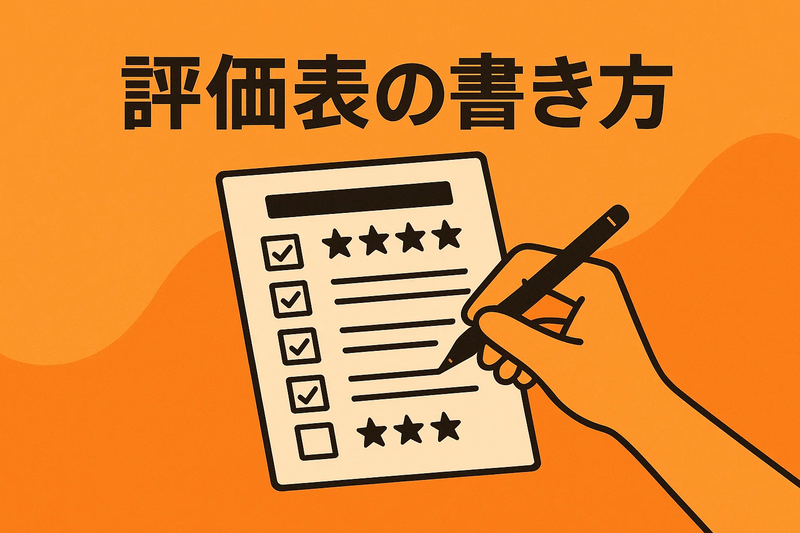
はじめに
「評価表ってどう書けばいいの?」 「評価項目や基準の決め方が分からない…」 「コメント欄に何を書けばいいのか毎回悩む」
といった方のために、今回は評価表の基本構成から書き方のコツ、職種別フォーマット、そして公平で納得感のある運用方法までをわかりやすくまとめました。
この記事を参考に、社員の成長を支援しながら組織全体の信頼性を高める理想の評価表づくりを実現してください。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
- はじめに
- 評価表の役割と目的(書く前に理解すべき3つのポイント)
- 評価表の書き方4ステップ
- 評価コメントの書き方
- 職種別・目的別の評価表フォーマット例
- 公平で納得感のある評価表にするためのポイント
- 人事評価に関わる試験をオンライン化するならWisdomBase
- まとめ
評価表の役割と目的(書く前に理解すべき3つのポイント)
 評価表は、単に社員の業績や行動を点数で示すためのものではありません。本来の目的は、組織として「公正な評価」を行いながら、社員一人ひとりの成長を支援することにあります。
評価表は、単に社員の業績や行動を点数で示すためのものではありません。本来の目的は、組織として「公正な評価」を行いながら、社員一人ひとりの成長を支援することにあります。
書き方のテクニックに入る前に、まずは評価表の本質的な役割を理解しておくことが大切です。ここでは、評価表を正しく活用するために押さえておきたい3つの視点を紹介します。
評価表は「公正な判断」と「成長促進」を両立させるツール
評価表の最大の役割は、「成果を公平に判断する」と同時に「社員の成長を促す」ことです。単に点数をつけるためではなく、評価を通じて現状の課題や強みを明確化し、次の行動につなげるフィードバックツールとして機能させることが理想です。
評価が透明で一貫していれば、社員は納得感を持ち、組織全体の信頼関係やモチベーションの向上にもつながります。
評価表の目的
評価表の目的は大きく3つあります。1つ目は、昇進・昇給などの人事判断に必要な「客観的な基準」を提供すること。2つ目は、社員のスキルや行動の変化を把握し「人材育成の指針」とすること。3つ目は、上司と部下の間で「成長を共有するコミュニケーションのきっかけ」を作ることです。つまり、評価表は組織運営の“指針書”でもあるのです。
よくある誤解
多くの管理職が陥りがちなのが、「評価表=査定表」という誤解です。
点数やランク付けだけに意識が向くと、評価が単なる判定作業になってしまいます。
しかし、本来の評価表は、社員の努力や成果を認め、次の成長につなげるための対話のベースです。書く目的を見失わず、「評価する側」と「される側」が共に納得できる形を目指しましょう。
評価表の書き方4ステップ
 評価表を効果的に活用するためには、単に「点数をつける」だけでなく、項目設定からコメント記入まで一貫した考え方を持つことが大切です。
評価表を効果的に活用するためには、単に「点数をつける」だけでなく、項目設定からコメント記入まで一貫した考え方を持つことが大切です。
評価表は、組織の目標と社員一人ひとりの成長を結びつける設計図のようなもの。構成や書き方を誤ると、評価が主観的になり、不公平感やモチベーション低下を招きかねません。
ここでは、評価表を作成・記入するうえで押さえておくべき4つのステップを解説します。
①評価項目を決める(業務成果・行動・スキル・プロセス)
最初のステップは「何を評価するのか」を明確にすることです。評価項目が曖昧だと、評価者によって判断が異なり、社員も何を目指せばいいのか分からなくなります。
一般的に評価項目は、以下の4つの軸で構成するのが効果的です。
- 業務成果(成果軸):売上、案件達成数、顧客満足度など、数字や結果に基づく評価。
- 行動(行動軸):チームワーク、報連相、主体性、責任感など、日常の行動や姿勢に関する評価。
- スキル(能力軸):専門知識、コミュニケーション力、課題解決力など、実務に必要なスキル。
- プロセス(過程軸):結果に至るまでの努力や工夫、問題への取り組み方など。
これらをバランスよく設定することで、短期的な成果だけでなく、成長や貢献度も正しく評価できるようになります。 また、各項目は職種や等級に合わせて調整し、全社員に共通する「基礎項目」と、部署ごとの「専門項目」に分けるとより実用的です。
②評価基準を明確にする(5段階評価・定性コメントの使い方)
次に重要なのが、評価基準を具体的に定義することです。例えば「5=非常に優れている」「3=標準的」「1=改善が必要」といった形で、誰が見ても同じ基準で判断できるようにします。
ただし、数値評価(定量評価)だけでは伝わらない部分も多いため、「なぜその評価になったのか」を言語化する定性コメントをセットで記入することが大切です。
たとえば「売上目標を120%達成した(成果)」という事実に加えて、「顧客課題を丁寧にヒアリングし、改善提案を積極的に行った点が評価できる(行動・スキル)」と具体的に説明することで、社員は自分の強みを理解しやすくなります。
また、評価者が複数いる場合は、全員が同じ基準で判断できるよう「評価基準ガイドライン」を共有しておくことも大切です。曖昧な言葉を避け、具体的な行動や成果の基準を明文化することで、公平性と一貫性が保たれます。
③評価コメントの書き方(良い例・悪い例・避ける言葉)
評価表で最も難しいのが「コメント欄の記入」です。コメントは、数字だけでは伝わらない“評価の根拠”を示す重要な部分であり、社員のモチベーションに大きな影響を与えます。
良い例:
- 「課題を自ら発見し、周囲を巻き込みながら改善に取り組む姿勢が見られた」
→ 主体的に課題解決に取り組む姿勢を記載。 - 「顧客対応において丁寧な言葉づかいと迅速な対応が評価できる」
→ 行動や成果を具体的に記述し、改善点よりも強みを中心に伝えている。
悪い例:
- 「頑張っていると思う」「もっと努力が必要」
→ 抽象的で根拠がなく、受け手が何を改善すれば良いか分からない。
避けるべき言葉は、人格を否定するような表現(例:「向いていない」「やる気がない」)や、曖昧な表現(「まあまあ」「普通」)は避けましょう。代わりに、「具体的な行動」や「期待値との比較」で伝えることが重要です。
たとえば、「報告が遅れることがある」という書き方ではなく、「次回は報告のタイミングを明確にし、チーム全体のスピードを上げられるとさらに良い」と前向きな改善提案を添えることで、受け手の意欲を引き出せます。
また、コメントを書く際は評価するために書くのではなく、成長を支援するために書くという視点を忘れないことが大切です。
④最終評価・フィードバック欄の記入ポイント
最終評価では、各項目の点数やコメントを総合的に整理し、社員の強み・課題・今後の目標を明確にまとめます。ここで重要なのは、「過去の評価」だけでなく「未来への期待」を含めることです。
たとえば、「課題発見力が高く、主体的に改善に取り組める点は強み。今後はチームメンバーへの指導力強化を期待したい」といった形で、次のステップを示すと良いでしょう。
フィードバック欄では、数値評価をそのまま伝えるのではなく、「なぜその評価になったのか」「どうすれば次はより良い評価を得られるのか」を明確に言語化します。これにより、社員が評価を受け入れやすくなり、改善行動にもつながります。
また、評価者と被評価者の対話を促す質問形式(例:「次回はどのスキルを伸ばしたいですか?」)を取り入れるのも効果的です。 こうした双方向のフィードバックを通じて、評価表は単なる「査定表」ではなく、「人を育てるための対話ツール」として機能するようになります。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
評価コメントの書き方
 評価コメントは、社員のモチベーションや今後の成長に直結する重要な要素です。
評価コメントは、社員のモチベーションや今後の成長に直結する重要な要素です。
単に「よかった」「改善が必要」と書くだけでは、受け手に何をどうすればよいかが伝わりません。
評価コメントは、評価の理由を明確にしつつ、社員の行動や努力を具体的に言語化することで初めて意味を持ちます。
ここでは、より効果的なコメントを書くための具体例や注意点を紹介します。
ポジティブコメント例
ポジティブコメントは、社員のやる気を引き出すうえで欠かせません。特に、成果だけでなく「過程」「姿勢」「成長」を評価する言葉を添えることで、社員は自分の努力が正しく認められていると感じます。
良い例:
- 「顧客対応のスピードと丁寧さが向上しており、顧客満足度の向上に貢献しています。」
- 「困難な課題にも前向きに取り組み、チーム内で良い影響を与えています。」
- 「新しい業務への挑戦意欲が高く、習得スピードも早い点が印象的です。」
- 「他部署との連携を意識し、円滑なコミュニケーションを実現しています。」
これらのコメントは、評価対象者の具体的な行動に焦点を当てています。
「すごい」「頑張っている」といった抽象的な表現ではなく、「何が」「どう良かったのか」を明確にすることで、社員が再現可能な行動として理解できるようになります。
ネガティブコメントを伝えるときの言い換えテクニック
改善点を伝える際には、言葉選びに細心の注意が必要です。
直接的な否定表現を使うと、相手のモチベーションを下げてしまう恐れがあります。
そのため、「できていない点」を指摘するよりも、「今後の期待」や「改善の方向性」を示す形に言い換えるのが効果的です。
悪い例:
- 「報告が遅い」「責任感が足りない」「主体性がない」
良い言い換え例:
- 「今後は、報告のタイミングを意識することで、よりスムーズな業務遂行が期待できます。」
- 「自ら提案や発信を増やすことで、リーダーシップの発揮につながるでしょう。」
- 「周囲との調整を早めに行うことで、成果がより安定する可能性があります。」
このように、指摘を「未来志向のメッセージ」に変換することで、相手に前向きな印象を与えつつ改善を促せます。重要なのは、「責める」ではなく「育てる」視点でコメントを書くことです。
避けるべきNGワードと曖昧表現
評価コメントで避けるべきなのは、根拠のない評価・人格否定・曖昧な表現の3つです。
NGワード例:
- 「やる気がない」「向いていない」「普通」「頑張っていない」
これらは、相手の感情を傷つけるだけでなく、具体的な改善策を示していないため、建設的な評価とは言えません。
また、「まあまあ」「特に問題ない」といった曖昧な言葉も避けるべきです。これらの表現では、相手に何を評価され、どこを改善すべきなのかが伝わらず、信頼関係を損なうこともあります。
代わりに、「〇〇の点は良かったが、□□の面を意識するとさらに良くなる」というように、肯定+改善提案の形で伝えることが理想です。こうした書き方を心がけると、受け手は前向きに受け止め、次の行動へとつなげやすくなります。
コメントの一貫性を保つチェックリスト
最後に、評価コメント全体の整合性を保つためのチェックポイントを紹介します。コメントがブレていると、評価の信頼性が下がり、社員の納得感も失われます。以下の点を意識して確認しましょう。
評価項目との整合性があるか
→ 評価コメントが、設定された項目(成果・行動・スキルなど)に対応しているか。評価基準に沿った表現になっているか
→ 「期待を上回った」「標準的」「改善が必要」など、基準と一致しているか。客観的な根拠があるか
→ 数字・事実・具体的なエピソードをもとに書かれているか。評価者の主観が入りすぎていないか
→ 感情的な表現や個人的な好みで判断していないか。フィードバック内容と矛盾していないか
→ 面談で伝える内容とコメントが一致しているか。
これらの項目をチェックすることで、コメントの信頼性と公平性が高まります。特に複数の評価者がいる場合は、同じ評価基準を共有し、表現の統一を意識することが重要です。
職種別・目的別の評価表フォーマット例
 評価表は、全社員に共通のフォーマットで管理することも大切ですが、実際には職種や役職、評価の目的によって適した項目や形式が異なります。
評価表は、全社員に共通のフォーマットで管理することも大切ですが、実際には職種や役職、評価の目的によって適した項目や形式が異なります。
たとえば、営業職とエンジニアでは成果の指標がまったく違うように、評価表もその業務内容に合わせて設計する必要があります。
ここでは、職種別・目的別に活用できる評価表のサンプルと、実際の作成・運用のポイントを紹介します。
一般社員・管理職・営業職・エンジニアなどのサンプル
まず、職種ごとに評価の焦点がどこにあるかを整理しましょう。
一般社員向け評価表
基本的な業務遂行能力、報連相(報告・連絡・相談)、チーム貢献度などを中心に評価します。特に、上司の指示を理解し、的確に実行できているかどうかが重要なポイントです。
管理職向け評価表
チームの成果、部下の育成、組織運営の安定性などを重視します。個人の成果だけでなく、「チームをどう導いたか」「課題をどう解決したか」というプロセス評価を含めることが重要です。
営業職向け評価表
売上達成率、顧客維持率、新規顧客獲得数などの定量評価を中心にします。ただし、成果だけでなく、「提案力」「顧客対応力」「信頼関係の構築」といった定性評価もバランスよく加えると、数字に現れにくい努力を正しく評価できます。
エンジニア向け評価表
コード品質、開発スピード、トラブル対応力、チーム内の技術共有などを評価軸に設定します。加えて、問題解決力や改善提案の積極性など、プロセス重視の項目を入れると、個々の貢献度をより正確に把握できます。
職種別に評価項目を明確化することで、社員が「何を目指せばよいのか」を理解しやすくなり、目標設定の質も向上します。
成果主義型/行動評価型/360度評価の違い
評価表の設計は、組織がどんな目的で評価を行うかによっても変わります。代表的な3つのタイプを見てみましょう。
成果主義型評価
数字や目標達成率など、結果を重視するタイプ。営業やマーケティングなど「成果が明確に可視化できる職種」に向いています。短期的なモチベーション向上には効果的ですが、過程や努力が軽視されるリスクがあります。
行動評価型評価
「どのように業務を遂行したか」に焦点を当て、行動指針や価値観の浸透を目的とします。チームワークやリーダーシップ、協調性など、数値化しにくい面を評価できるのが特徴です。
360度評価
上司だけでなく、同僚や部下、他部署など複数の視点から評価する方法です。自己評価とのギャップを可視化し、客観性を高める効果があります。人材育成やリーダー研修において特に有効です。
Excel/Googleスプレッドシートでの作成例
多くの企業では、評価表をExcelまたはGoogleスプレッドシートで作成・管理しています。これらのツールを使えば、手軽に評価項目を設定し、スコアを自動集計することも可能です。
作成のポイントは、以下の通りです。
- 評価項目を縦軸、社員名を横軸に配置し、誰がどの項目をどのように評価するかを明確にする。
- 数値評価とコメント欄をセットで設けることで、定量・定性の両面から判断できる。
- 条件付き書式や関数(AVERAGE、IFなど)を活用して、平均値や評価分布を自動計算。
- Googleスプレッドシートの場合はリアルタイム共有が可能なため、複数の評価者による同時入力やコメントがしやすい。
テンプレートを使うときの注意点
ネット上には無料・有料を問わず多くの評価表テンプレートがありますが、そのまま利用するのは危険です。 テンプレートはあくまで「参考用」であり、自社の業務内容・文化・評価方針に合わせてカスタマイズする必要があります。 特に注意すべきは以下の3点です。
- 評価項目が抽象的すぎないか確認する(例:「責任感がある」「主体的である」などの表現を具体化)
- 職種ごとの指標が反映されているかを見直す(営業とエンジニアでは基準が異なる)
- 評価基準の説明文を追加する(「4=期待を上回る」「3=標準」などを明記)
さらに、テンプレートの導入時には評価者研修を行い、使い方や基準の共通理解を深めることが大切です。フォーマットだけが整っていても、運用ルールが統一されていなければ、評価の信頼性は担保されません。
公平で納得感のある評価表にするためのポイント
 評価表の最大の目的は、社員が「公正に評価されている」と実感できることです。どんなに評価項目を整えても、評価者の判断がバラついたり、説明が不十分だったりすれば、社員の不満や不信感につながります。
評価表の最大の目的は、社員が「公正に評価されている」と実感できることです。どんなに評価項目を整えても、評価者の判断がバラついたり、説明が不十分だったりすれば、社員の不満や不信感につながります。
評価制度を信頼される仕組みにするためには、「属人化を防ぐルール」「バイアスを抑える工夫」「誠実なフィードバック」「成長を促す対話」の4つを意識することが重要です。
評価の属人化を防ぐルール設計
評価の属人化とは、評価者によって判断基準や厳しさが異なってしまう状態を指します。これを防ぐには、まず評価基準の明文化が欠かせません。
たとえば「チーム貢献度を5点とする基準は何か」を明確に文書化し、全評価者で共有します。さらに、複数評価者制度(一次・二次評価)を導入すると、個人の主観に左右されにくくなります。
会議形式で複数の管理職が意見を出し合う「評価調整会議」も効果的です。また、評価の背景やコメントの根拠を残しておくことで、後から見返しても一貫性のある評価が行えるようになります。
評価者のバイアスを減らす工夫
評価者には無意識の偏り(バイアス)が存在します。たとえば「印象が良い人を高く評価する(ハロー効果)」や「最近の出来事に影響される(近時効果)」などです。これを防ぐには、具体的な事実を記録する習慣がおすすめです。
日々の業務での成果や行動をメモしておくことで、感情に流されず、客観的に評価できます。さらに、評価者研修を実施し、バイアスの種類や防ぎ方を理解させることも重要です。
チェックリストを使って「感情ではなくデータで判断できているか」を確認すると、より公平性が高まります。
フィードバック面談で信頼関係を築く方法
評価は、点数をつけて終わりではありません。社員が納得し、次の行動に移れるかどうかは、フィードバック面談の質にかかっています。まずは「一方的に伝える」ではなく、対話型の面談を意識しましょう。「今回の評価についてどう感じましたか?」と質問し、相手の意見を尊重する姿勢が大切です。
また、改善点だけでなく「良かった点」から話し始めることで、防御的な態度を防ぎ、前向きな話し合いができます。最後には「次にどんな目標を目指すか」を一緒に設定し、成長へのロードマップを共有することが信頼関係の構築につながります。
評価を「成長対話」に変えるための工夫
評価は、社員を“査定する”ものではなく、成長を支援するための対話の機会に変えることが理想です。そのためには、過去ではなく未来に焦点を当てることがポイントです。
「なぜできなかったのか」ではなく、「次にどう活かせるか」を一緒に考える姿勢が大切です。また、面談時に社員の強みを具体的に言語化し、それを活かせる業務を提案すると、モチベーションの向上につながります。
さらに、評価結果を基に研修やスキルアップの計画を立てることで、評価表は人材育成ツールとして機能します。
人事評価に関わる試験をオンライン化するならWisdomBase
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
当社では、オンライン試験システム「WisdomBase」を提供しています。試験をはじめとする社内試験のオンライン化をサポートし、「不正防止」「運営効率化」「社員の納得感向上」といった課題を解決してきました。
WisdomBaseは、制限時間や出題形式を柔軟に設定できるほか、カメラ監督による不正対策機能や、数百人規模の同時受験にも対応できる高い安定性を備えています。
すでに全国規模で社員試験を行う企業にも導入され、従来の工数・コストを大幅に削減するとともに、公平性と透明性の高い試験運営を実現しています。試験のオンライン化をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 wisdombase.share-wis.com wisdombase.share-wis.com
まとめ
評価表は、「成果を数値化するもの」ではなく、「人の成長を支援するツール」であることを忘れてはいけません。
評価者がその本質を理解し、適切な基準・コメント・フィードバックを用意することで、評価は“査定”から信頼の対話へと変わります。
評価表の書き方を正しく理解し、仕組みとして運用することで、社員が安心して成長できる環境が生まれ、結果的に組織全体の生産性と信頼が向上します。 公正さと納得感、そして積極的な評価文化を両立させること。それが、これからの時代に求められる人事評価のあり方です。

