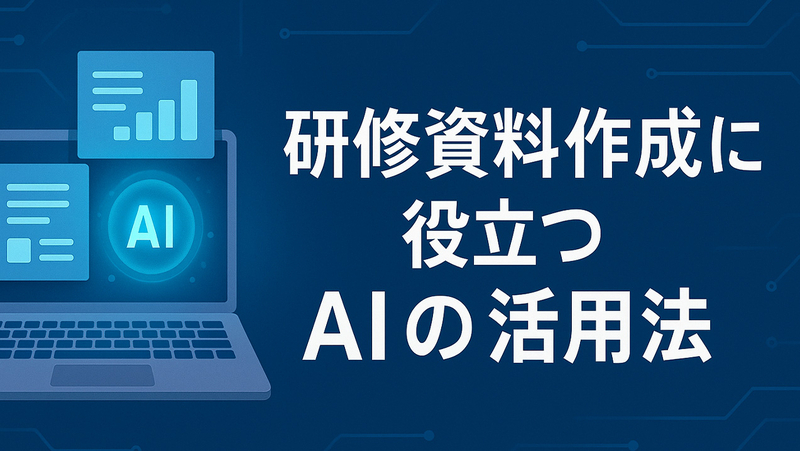
はじめに
新年度の研修準備を前に、膨大な資料作成の山を見てため息をついていませんか?毎年同じようなスライドを少し手直しするだけの日々に、どこか物足りなさや危機感を覚えていませんか?
あるいは、上司から「これからはAIの時代だ。研修資料もAIで効率的に作ってくれ」と、期待とプレッシャーの入り混じった指示を受け、何から手をつけていいか途方に暮れている方もいるでしょう。時間はない、でも品質は落とせない。外部委託コストは削減したい。そんな八方塞がりの状況は、もはや研修担当者の「あるある」です。
この記事は、そんなあなたのための「処方箋」です。AIを単なる効率化ツールとしてではなく、あなたの創造性を加速させ、研修の質を劇的に向上させる戦略的パートナーとして使いこなすための、具体的で実践的な方法を余すところなく解説します。
- はじめに
- AIを活用した研修資料作成の利点
- 研修資料作成に役立つAIツールの紹介
- AIのハルシネーション現象とその対策
- AIを使った研修資料作成における著作権の問題
- AIを効果的に研修資料作成に活かす方法
- オンラインでの研修にWisdomBase
AIを活用した研修資料作成の利点

AIを研修資料作成に導入することは、単なる流行への追従ではありません。それは、研修の質と効率を根本から変革する戦略的な一手です。これまで資料作成に費やしていた膨大な時間を大幅に削減できるだけでなく、コンテンツの質そのものを高める可能性を秘めています。
AIは、構成案の立案からデザインの自動生成、さらには受講者の反応に基づいた改善提案まで、研修担当者の強力なパートナーとなり得ます。ここでは、AIがもたらす具体的なメリットを掘り下げ、あなたの研修準備プロセスがどのように進化するのかを明らかにします。AIの力を正しく理解し、活用することで、あなたはより本質的な業務、つまり「どうすれば受講者の成長を最大化できるか」という問いに集中できるようになるのです。
AIがもたらす効率化のポイント
AI活用による最大の魅力は、なんといっても圧倒的な時間効率の向上です。生成AIは特定の業務において、従来の方法と比較して60〜70%もの時間削減効果をもたらす可能性があると言われています。これを研修資料作成に当てはめてみましょう。例えば、20時間かかっていた新人研修用のスライド(50枚)作成が、AIの補助によって6〜8時間で完了するイメージです。
具体的には、AIは以下のプロセスを高速化します。
- 構成案の壁打ち・立案
- 「新人営業向けのビジネスマナー研修」といったテーマを投げかけるだけで、数分で網羅的なアジェンダを複数パターン提案してくれます。
- 原稿執筆
- 各スライドに記載するテキストのたたき台を瞬時に生成。冗長な表現の修正や、専門用語の平易な言い換えなども一瞬です。
- デザイン・レイアウト
- テキスト原稿を基に、見栄えの良いスライドデザインを自動で生成。配色やフォント、画像の配置に悩む時間が激減します。
これらの作業をAIに任せることで、担当者はコンテンツの事実確認や、自社の文脈に合わせた表現の調整など、より創造的で重要な業務に集中できるようになります。
自動生成コンテンツの精度
「AIが作ったコンテンツなんて、どうせ質が低いだろう」そう考えるのは早計かもしれません。近年のAI、特に大規模言語モデル(LLM)の進化は目覚ましく、生成される文章の自然さや論理構成の的確さは、人間が作成したものと遜色ないレベルに達しつつあります。
もちろん、AIは完璧ではありません。専門性が非常に高い分野や、最新の社内情報など、学習データに含まれていない情報については、不正確な内容を出力する「ハルシネーション」という現象も起こり得ます。
しかし、一般的なビジネスマナーやコンプライアンス、基本的なITスキルといった普遍的なテーマであれば、AIが生成するコンテンツは非常に質の高い「たたき台」として機能します。重要なのは、AIの生成物を「完成品」と捉えるのではなく、「優秀なアシスタントが用意してくれた初稿」と位置づけることです。この初稿を基に、専門家であるあなたがファクトチェックを行い、自社の事例や価値観を肉付けしていくことで、短時間で高品質なオリジナルコンテンツを生み出すことが可能になるのです。
【関連記事】 wisdombase.share-wis.com
研修資料のカスタマイズ性向上
画一的な研修資料では、多様なバックグラウンドを持つ受講者全員の心に響かせることは困難です。しかし、受講者の役職や職種、スキルレベルに合わせて複数のパターンの資料を用意するのは、人的リソースの観点から現実的ではありませんでした。AIは、この課題に対する強力な解決策となります。
例えば、ベースとなる研修資料を一つ作成した後、AIに「この内容を、IT部門の新人向けに専門用語を補足して書き直して」「このスライドを、マネージャー向けの要約版にして」といった指示を出すだけで、瞬時に複数のバージョンを生成できます。これにより、受講者一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズドラーニングの実現に大きく近づきます。
また、デザイン面でも「当社のコーポレートカラーである青を基調としたデザインに変更して」といった指示で、簡単にブランドイメージに沿った資料にカスタマイズできるため、資料全体の統一感を保ちながら、多様なニーズに応えることが可能になります。
データ分析を活用した資料改善
研修は実施して終わりではありません。その効果を測定し、次回の改善に繋げるPDCAサイクルを回すことが不可欠です。AIは、この「Check(評価)」と「Action(改善)」のフェーズにおいても大きな力を発揮します。
従来、研修後のアンケート結果は、担当者が一つひとつ目視で確認し、感覚的に改善点を探ることが一般的でした。これでは、担当者の主観に頼りがちになり、本質的な課題を見逃す可能性もあります。
AIを活用すれば、大量のアンケートデータ(自由記述含む)を瞬時に分析し、「『〇〇』という用語の説明が分かりにくいという意見が多数」「△△のセクションで離脱率が高い」といった客観的なインサイトを抽出できます。さらに、理解度テストの結果と研修内容を突き合わせ、どの部分が受講者の理解度に繋がり、どの部分が繋がらなかったのかを特定することも可能です。これらのデータに基づいた改善を行うことで、研修資料は回を重ねるごとに洗練され、その効果を最大化していくことができるのです。
AI活用で避けるべき落とし穴
AIは強力なツールですが、万能の魔法の杖ではありません。その導入には、注意すべき「落とし穴」が存在します。最も注意すべきは、AIへの過度な依存です。AIが生成したコンテンツを鵜呑みにし、ファクトチェックや内容の吟味を怠ると、誤った情報を社内に拡散してしまうリスクがあります。特に、法律やコンプライアンスに関わる研修では、一つの間違いが大きな問題に発展しかねません。
また、効率化を追求するあまり、研修の「魂」が失われる危険性もあります。自社の成功事例や失敗談、創業者の想いといった、血の通ったストーリーは、受講者の共感やエンゲージメントを高める上で不可欠な要素です。AIは論理的な文章を生成するのは得意ですが、こうした人間的な熱量や文脈を完全に再現することはできません。AIをあくまで「アシスタント」と位置づけ、最終的な仕上げは担当者自身が魂を込めて行うという姿勢が、質の高い研修を実現する鍵となります。ツールの性能に振り回されず、目的を見失わないことが重要です。
研修資料作成に役立つAIツールの紹介

AIと一言でいっても、その種類や機能は多岐にわたります。研修資料作成という目的を達成するためには、どのようなAIツールを、どのように選べば良いのでしょうか。このセクションでは、具体的なツール名や活用事例を交えながら、あなたの「右腕」となるAIツールを見つけるための指針を示します。文章の生成、スライドデザインの自動化、さらには無料で使える便利なツールまで、明日からの資料作成が劇的に変わる情報を網羅しました。
ツールの特徴を正しく理解し、自社の状況や目的に合わせて賢く選択することが、AI活用の第一歩です。ここで紹介するツールや選び方のポイントを押さえれば、あなたはもうツール選びで迷うことはありません。
自然言語処理ツールの選び方
研修資料の根幹をなす「文章」を作成・編集する上で、自然言語処理(NLP)に長けたAIツールは欠かせません。代表的なものに、OpenAI社の「ChatGPT」、Google社の「Gemini」などがあります。これらのツールを選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 目的との適合性:
- ブレインストーミングや構成案作成
- 創造性が高く、多様なアイデアを出してくれる「ChatGPT」や「Gemini」が適しています。
- 長文の要約や校正
- 長い文章の読解・生成能力に定評のある「Claude」が強みを発揮します。既存の長いマニュアルを要約して研修資料の元にする、といった用途に向いています。
- ブレインストーミングや構成案作成
- 最新情報への対応
- 研修内容によっては、最新の法改正や市場動向を反映させる必要があります。Webブラウジング機能を持ち、最新情報にアクセスできるか(例: ChatGPTの有料プラン、Geminiなど)は重要な選定基準です。
- セキュリティ
- 企業の機密情報や個人情報を含む内容を扱う場合は、入力したデータがAIの学習に使われない「オプトアウト申請」が可能か、あるいは法人向けのセキュリティが強化されたプラン(例: ChatGPT Enterprise, Gemini for Google Workspace)があるかを確認することが必須です。
自動レイアウト生成ツールの活用事例
テキストさえ用意すれば、AIが自動でデザイン性の高いスライドを生成してくれる。そんな夢のようなツールがすでに実用化されています。これらのツールを使えば、デザインの知識がなくても、プロが作成したような見栄えの良い資料を短時間で作成できます。
- Gamma
- 「〇〇についてのプレゼン資料」と入力するだけで、構成案からテキスト、関連画像まで含んだスライドを数十秒で生成します。手軽さと生成スピードが魅力で、まずはAIによる資料作成を体験してみたいという場合に最適です。
- Tome
- ストーリーテリングに特化したAIプレゼンテーションツール。単なる情報の羅列ではなく、聞き手の心に響く物語性のある構成を自動で組み立ててくれます。新入社員に向けた企業理念の浸透研修などで効果を発揮するでしょう。
- Beautiful.ai
- デザインテンプレートの豊富さと、レイアウトの自動調整機能が特徴です。要素を追加・削除しても、AIが常に最適なレイアウトを保ってくれるため、デザイン崩れを気にすることなく編集に集中できます。
活用事例
ある企業の人事担当者は、毎年1週間かけていた新人研修用のコンプライアンス資料作成にGammaを導入。AIが生成したたたき台を基に、自社の事例を追加・修正するだけで、わずか1日で資料を完成させ、残りの4日間をコンテンツの質の向上や、他の研修準備に充てることができました。
コンテンツ推薦AIの展望
現在のAI活用は、主に「作成」の効率化に焦点が当てられていますが、将来的には「何を学ぶべきか」という「推薦」の領域でAIがさらに重要な役割を果たすようになります。例えば、社員一人ひとりのスキルセット、キャリアプラン、過去の受講履歴などをAIが分析し、「あなたには今、この研修が必要です」と、パーソナライズされた学習コンテンツを自動で推薦してくれる世界の到来です。
研修担当者は、全社員に同じ内容を提供するのではなく、個々の能力開発に最適化された学習パスをデザインする「ラーニングアーキテクト」としての役割がより重要になります。AIが個々の学習進捗をリアルタイムで把握し、つまずいているポイントがあれば、補足資料を自動で提供したり、メンターとの面談をセッティングしたりといった、きめ細やかなフォローも可能になるでしょう。これはまだ未来の話に聞こえるかもしれませんが、すでに一部のLMS(学習管理システム)では、AIによるレコメンド機能が搭載され始めており、研修の個別最適化は着実に進んでいます。
無料で使えるAIツールのリスト
AIツールの導入にはコストがかかると思われがちですが、無料で始められる、あるいは既存のツールに搭載されている強力なAI機能も数多く存在します。まずはこれらから試してみるのが、AI活用の賢い第一歩です。
- Microsoft Copilot
- Microsoftアカウントがあれば無料で利用でき、最新のWeb情報に基づいた回答を生成してくれます。GPT-4を搭載しており、高性能な文章生成が可能です。EdgeブラウザでPDFを開き、その内容について質問や要約を指示することもできます。
- Canva (Magic Design)
- デザインツールとしておなじみのCanvaにも、強力なAI機能が搭載されています。キーワードをいくつか入力するだけで、複数のデザインパターンのプレゼンテーションを自動生成してくれます。豊富なテンプレートや素材と組み合わせることで、デザイン性の高い資料が簡単に作れます。
- PowerPoint (AI機能)
- Microsoft 365のサブスクリプションをお持ちの場合、PowerPointにも「デザイナー」というAI機能が標準で搭載されています。箇条書きのテキストを入力するだけで、それを視覚的に表現するデザインアイデアを複数提案してくれます。
- ChatGPT (無料版)
- 有料版ほどの高性能ではありませんが、研修の構成案作成や文章のたたき台作りには十分な性能を持っています。まずは無料版でAIとの対話に慣れるのが良いでしょう。
AIツール選択時のポイント
数あるAIツールの中から自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な視点があります。以下のポイントをチェックリストとして活用し、総合的に判断しましょう。
- セキュリティは万全か
- これが最も重要です。企業の機密情報や個人情報を扱う可能性がある以上、入力データがどのように扱われるかを必ず確認してください。法人向けプランや、データのプライバシー保護を明確にうたっているツールを選びましょう。
- 日本語への対応レベル
- 海外製のツールが多いため、日本語の処理精度やユーザーインターフェースの日本語対応は必ず確認が必要です。自然な日本語の文章を生成できるか、デモや無料トライアルで試すことをお勧めします。
- 操作性は直感的か
- 導入しても使いこなせなければ意味がありません。ITに不慣れな人でも直感的に操作できるか、マニュアルを読まなくてもある程度使えるかが重要です。
- コストパフォーマンス
- 無料で使える範囲はどこまでか、有料プランの料金体系は自社の予算に見合っているかを確認します。単機能の安価なツールを組み合わせるか、多機能な高価格帯のツールを一つ導入するか、費用対効果を慎重に検討しましょう。
- 連携機能
- すでに社内で利用しているツール(例: Microsoft 365, Google Workspace, Slackなど)と連携できるかも重要なポイントです。ツール間の連携がスムーズであれば、業務効率は飛躍的に向上します。
AIのハルシネーション現象とその対策

AIの活用を検討する上で、避けては通れないのが「ハルシネーション」という現象です。これは、AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまうことを指します。この現象を正しく理解し、適切な対策を講じなければ、研修で誤った知識を教えてしまうという重大な事態になりかねません。ハルシネーションがなぜ起こるのか、どのような状況で発生しやすいのかを知り、その見極め方を身につけることで、リスクを管理しながらAIの恩恵を安全に享受することができます。
このセクションでは、ハルシネーションの正体から具体的な対策までを詳しく解説し、あなたが安心してAIを使いこなすための知識を提供します。
ハルシネーションとは何か
ハルシネーション(Hallucination)とは、日本語で「幻覚」を意味する言葉です。AIの文脈では、「AIが、学習データに含まれていない、あるいは事実と異なる情報を、あたかも真実であるかのように、もっともらしく生成する現象」を指します。例えば、「日本の首都は京都です」と堂々と回答したり、存在しない法律の条文や、架空の学術論文を引用したりするケースがこれに当たります。
これはAIの「バグ」や「故障」ではありません。生成AIは、次に続く単語の確率的な連なりを予測して文章を組み立てています。そのため、学習データに偏りがあったり、質問の意図を正確に解釈できなかったりした場合に、統計的に「それらしい」言葉を繋ぎ合わせた結果、事実とは異なる内容が出来上がってしまうのです。AIは自分が嘘をついているという自覚がないため、その出力は自信に満ち溢れており、見分けるのが難しい場合があります。
発生しやすいシチュエーション
ハルシネーションは、どのような状況で発生しやすいのでしょうか。以下のシチュエーションでは特に注意が必要です。
- 専門性が極めて高い分野
- ニッチな業界の専門知識や、特定の企業内でのみ通用する用語など、AIの学習データが少ないトピックについて質問すると、不正確な情報が生成されやすくなります。
- 最新の出来事
- AIモデルの学習データは、ある特定の時点までの情報でカットオフされています(これをナレッジカットオフと呼びます)。そのため、それ以降に起こった出来事や、発表された最新情報について尋ねると、古い情報に基づいて回答したり、情報を捏造したりすることがあります。
- 固有名詞や数値データ
- 人名、社名、製品名といった固有名詞や、統計データ、日付、金額などの具体的な数値は、AIが間違いやすいポイントです。特に、複数の情報を組み合わせて複雑な回答を生成させようとすると、細部で誤りが生じやすくなります。
- 曖昧な質問や複雑な指示
- 質問の意図が不明確であったり、一度に多くの条件を盛り込んだりすると、AIが指示を正しく理解できず、文脈に合わない、あるいは事実と異なる回答を生成する可能性が高まります。
ハルシネーションの発生を防ぐ方法
ハルシネーションを100%防ぐことは現時点では不可能ですが、その発生確率を大幅に下げるための工夫はいくつか存在します。これを「プロンプトエンジニアリング」と呼びます。
- 情報源を指定する
- 質問の際に、「〇〇社の公式ウェブサイトの情報を基に回答してください」や「添付した社内規定のPDFに基づいて説明してください」のように、参照すべき情報源を具体的に指定することで、AIが自由に「創作」するのを防ぎます。
- 段階的に質問する
- 一度に複雑な指示を出すのではなく、「まず〇〇の概要を説明して」「次に、そのメリットとデメリットを3つずつ挙げて」というように、タスクを分解して一つずつ指示を出すことで、AIは各ステップに集中し、より正確な回答を生成しやすくなります。
- 「知らない場合は『不明』と答えて」と指示する
- プロンプトの最後に「もし情報が不確かな場合は、推測で答えずに『不明』と回答してください」という一文を加えることで、AIが無責任な回答をすることを抑制する効果が期待できます。
- 複数のAIでクロスチェックする
- 同じ質問をChatGPT、Gemini、Claudeなど複数の異なるAIに投げかけ、回答を比較検討します。全てのAIが同じ内容を回答すれば、その情報の確度は高いと判断できます。回答が分かれた場合は、その点がファクトチェックの必要な箇所であると特定できます。
AIによる誤情報の見極め方
AIの出力は、必ず人間が最終確認を行うという原則を徹底することが、誤情報を見極める上で最も重要です。以下の点を意識してチェックしましょう。
- 出典の確認
- AIが何らかの情報源(論文、ニュース記事、ウェブサイトなど)を提示した場合、その出典が実在するか、リンクが有効かを必ず確認します。存在しない出典を捏造することは、ハルシネーションの典型的なパターンです。
- ダブルチェックの習慣化
- 特に、法律、数値、固有名詞などの重要な情報については、必ず公式な情報源(官公庁のウェブサイト、企業の公式発表、信頼できる報道機関など)で裏付けを取る習慣をつけましょう。
- 文脈の不自然さ
- 一見流暢な文章に見えても、よく読むと論理が飛躍していたり、文脈に合わない単語が使われていたりすることがあります。「何となく違和感がある」という直感を大切にし、その部分を重点的に調べましょう。
- 過度に断定的な表現への注意
- 「絶対に」「間違いなく」「唯一の」といった強い断定表現が使われている場合、AIが過信している可能性があります。現実はそれほど単純ではないケースが多いため、疑いの目を持つことが重要です。
導入前に検討すべきリスク
研修資料作成にAIを本格導入する前に、ハルシネーションがもたらす潜在的なリスクを組織として認識し、対策を講じておく必要があります。
- 信用の失墜
- 研修で誤った情報を教えてしまった場合、受講者からの信頼を失うだけでなく、講師や人事部門、ひいては会社全体の信用問題に発展する可能性があります。
- コンプライアンス違反
- 法律や業界規制に関する研修でハルシネーションによる誤情報を提供した場合、意図せずコンプライアンス違反を助長してしまうリスクがあります。
- 業務上の損害
- 誤った業務手順や操作方法を教えてしまった結果、実際の業務でミスや事故が発生し、直接的な損害に繋がる可能性もゼロではありません。
これらのリスクを回避するためには、AI利用に関する社内ガイドラインの策定が不可欠です。「AI生成物は必ず人間がファクトチェックを行う」「機密情報や個人情報の入力は禁止する」「著作権を侵害する可能性のある利用は行わない」といったルールを明確にし、全社で周知徹底することが、安全なAI活用のための第一歩となります。
AIを使った研修資料作成における著作権の問題

AIによるコンテンツ生成の効率化は魅力的ですが、その裏には「著作権」という複雑な法的問題が潜んでいます。AIが生成した文章や画像の権利は誰に帰属するのか?学習データに含まれる第三者の著作物を利用しても問題ないのか?AIと共同で作成した研修資料を、どこまで自由に利用できるのか?これらの問いに明確に答えられないままAI活用を進めることは、思わぬ法的トラブルに巻き込まれるリスクを伴います。
このセクションでは、研修担当者が最低限知っておくべきAIと著作権の基本を、日本の法律(2024年時点の見解)を踏まえながら、分かりやすく解説します。法的なリスクを正しく理解し、安心して創造的な活動に集中するための知識を身につけましょう。
AIが生成するコンテンツの著作権
まず最も基本的な疑問として、「AIが生成したコンテンツに著作権は発生するのか?」という点があります。日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。そして、その創作活動の主体は「人間」であることが前提とされています。
したがって、人間が全く関与せず、AIが自律的に生成したコンテンツ(例えば、キーワードを1つ入れただけで自動生成された文章や画像)には、原則として著作権は発生しないというのが現在の一般的な考え方です。著作権が発生しないということは、誰でも自由に利用できる反面、他者による無断利用を防ぐ権利もない、ということになります。
ただし、人間がプロンプト(指示)を工夫したり、AIの生成物を何度も修正・加工したりするなど、人間の「創作的寄与」が認められる場合は、その生成物全体に人間の著作物として著作権が発生する可能性があります。研修資料作成においては、AIの生成物をたたき台とし、担当者が大幅に加筆・修正を加えるケースが多いため、最終的な資料には担当者の著作権が認められる可能性が高いと言えるでしょう。
第三者コンテンツの利用時の注意点
AIは、インターネット上の膨大なテキストや画像データを学習してコンテンツを生成します。この学習データには、当然ながら著作権で保護されたコンテンツも含まれています。ここで問題となるのが、AIが生成したコンテンツが、学習元となった特定の著作物と酷似してしまう「意図せぬ著作権侵害」のリスクです。
例えば、AIに「有名なキャラクター風のイラスト」を生成させた場合、そのキャラクターの著作権を侵害する可能性が非常に高くなります。文章においても、特定の書籍や記事の表現と酷似したものが生成されるリスクはゼロではありません。
対策としては、以下の点が挙げられます。
- 生成物の類似性チェック
- 特に画像やデザインなど、独創性が重要なコンテンツについては、Google画像検索などを使って類似の作品が存在しないかを確認する。
- 商用利用可能なAIツールを選ぶ
- 企業によっては、学習データが著作権フリーの素材や、ライセンス許諾を得たデータのみで構成されていることを保証しているAIサービスもあります。商用利用を前提とする場合は、こうしたツールの利用がより安全です。
- 社内利用に留める
- 作成した研修資料を社内での利用に限定する場合、著作権侵害のリスクは比較的低いとされています。しかし、ウェブサイトで公開したり、販売したりする場合は、より一層の注意が必要です。
研修資料を公開する際の法的留意点
AIを用いて作成した研修資料を、社内だけでなく社外(例えば、自社のウェブサイトでの公開、セミナーでの配布、eラーニングコンテンツとしての販売など)で利用する場合には、特に慎重な検討が必要です。
まず、前述の通り、意図せず第三者の著作権を侵害していないかを徹底的に確認する必要があります。万が一、著作権侵害の訴えを起こされた場合、企業の信頼失墜や損害賠償に繋がる可能性があります。
次に、AIが生成した画像に、実在の人物と見分けがつかないほどリアルなものが含まれている場合、その人物の肖像権やパブリシティ権を侵害するリスクも考慮しなければなりません。
これらのリスクを回避するためには、社外に公開する資料については、AIによる自動生成部分を減らし、オリジナルのテキストや、ストックフォトサービスなどで正規にライセンスを取得した画像を中心に構成するのが最も安全なアプローチと言えるでしょう。AIを利用する場合は、あくまでアイデア出しや構成案の作成といった「補助的」な役割に留めるのが賢明です。
AIとの共同作成における権利関係
研修担当者がAIを駆使して資料を作成した場合、その著作権は誰のものになるのでしょうか。これは「共同著作物」の考え方に関わってきます。現状の法解釈では、AIは著作権の主体とはなり得ないため、AIと人間が「共同著作権者」になることはありません。
創作的な関与を行った人間、つまり研修担当者自身が著作権者となります。会社員が職務として作成した研修資料の場合、通常は法人(会社)が著作者となる「職務著作」の規定が適用されることがほとんどです。
重要なのは、社内でAI利用のルールを明確にしておくことです。例えば、「AIを利用して作成した資料の著作権は、職務著作の規定に基づき会社に帰属する」といった内容を就業規則やAI利用ガイドラインに明記しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。担当者が個人的に契約しているAIツールで作成した資料の権利関係など、曖昧になりがちな部分を明確にしておくことが重要です。
AI開発企業とコンテンツ権利者の間では、権利の境界線がまだ確立されていない部分が多いです。研修資料を作成する一担当者として、こうした世界的な動向を完全に把握する必要はありませんが、「AIが生成するコンテンツは、法的にグレーな部分を多く含んでいる」というリスク意識を持つことが、自社と自身を守る上で非常に重要になります。
AIを効果的に研修資料作成に活かす方法

AIの利点やリスクを理解した上で、いよいよ実践的な活用フェーズに入ります。大切なのは、AIを単独のツールとして使うのではなく、複数のツールや手法を組み合わせ、自社の目的に合わせて最適化していくことです。AIは、あなたの指示を待つだけの受動的な道具ではありません。創造的なパートナーとして、コンテンツのブラッシュアップから新しいアイデアの創出まで、様々な形であなたの仕事をサポートしてくれます。
この最終セクションでは、AIの能力を最大限に引き出し、研修資料の品質と作成効率を飛躍的に向上させるための、より高度で効果的な活用法を紹介します。明日からあなたの研修準備は、単なる「作業」から、AIと共に未来を創造する「プロジェクト」へと進化するでしょう。
ツールの効果的な組み合わせ方
AIツールの真価は、それぞれが得意な領域を理解し、ワークフローの中で効果的に組み合わせることで発揮されます。単一のツールで全てを完結させようとするのではなく、リレーのようにタスクを渡していくイメージです。
ワークフロー例:新人営業研修「テレアポの基本」資料作成
- 構成案作成 (ChatGPT/Gemini)
- プロンプト
「法人営業の新人向けに、テレアポの基本を学ぶ90分の研修を企画しています。心構え、事前準備、トークスクリプト、断られた際の対応、成功事例の5つの要素を盛り込んだ研修のアジェンダを作成してください。」
- AIが生成したアジェンダを基に、全体の流れを確定させます。
- プロンプト
- 各章の原稿執筆 (Claude/ChatGPT)
- プロンプト
「上記アジェンダの『事前準備』について、スライド3枚分の原稿を作成してください。ターゲットリストの作成、企業リサーチ、トークスクリプト準備の3つのポイントを、具体的なアクションと共に解説してください。」
- 生成された原稿を、自社の営業スタイルに合わせて修正・加筆します。
- プロンプト
- スライドデザイン生成 (Gamma/Canva)
- 完成したテキスト原稿をGammaに貼り付け、スライドを自動生成させます。あるいは、CanvaのMagic Designで、テキストを基にしたデザイン案を複数出力させ、最もイメージに近いものを選択します。
このように、各AIの強みを活かして連携させることで、一人で作業するよりも遥かに速く、質の高い資料を作成することが可能になります。
AIによるコンテンツの見直し
AIの活用は、新規作成だけにとどまりません。むしろ、既存の研修資料をブラッシュアップする際にこそ、その真価を発揮すると言えます。長年使い続けてきた「秘伝のタレ」のような資料も、AIという客観的な視点を通すことで、新たな改善点が見つかります。
- 表現の平易化
- 既存の資料をAIに読み込ませ、「この文章を、社会人経験のない新入社員でも理解できるように、専門用語を使わずに書き直してください」と指示します。これにより、誰にとっても分かりやすい資料に生まれ変わります。
- 要約とキーメッセージ抽出
- 長大なマニュアルや報告書から、研修で伝えるべき核心部分だけをAIに要約させます。「この50ページの資料から、研修で伝えるべき最も重要なポイントを5つに絞ってください」といった指示が有効です。
- 多角的な視点の追加
- 「この資料の内容について、受講者から出そうな質問を5つ予測してください」あるいは「この主張に対する反対意見や懸念点を挙げてください」とAIに問いかけることで、内容の網羅性を高め、より深い議論を促す資料にすることができます。
異なるAI同士の連携による新たな可能性
一歩進んだ活用法として、異なる種類のAIをAPI連携(プログラムを通じてツール同士を接続すること)させることで、これまでにない価値を生み出すことも可能です。専門的な知識が必要な場合もありますが、将来的にはより簡単に連携できるようになるでしょう。
- 音声合成AIとの連
- ChatGPTで作成した研修の台本を、API経由で音声合成AIに渡し、人間のように自然なナレーション付きの研修動画を自動で生成します。これにより、動画コンテンツの内製化が容易になります。
- 文字起こしAIとの連携
- 熟練社員の営業トークやプレゼンテーションを録音し、文字起こしAI(例: Whisper)でテキスト化します。そのテキストを要約・体系化するよう言語モデルAIに指示し、優れたノウハウを形式知化して研修資料に落とし込みます。
- データ分析AIとの連携
- 研修後のアンケート結果(自由記述)を言語モデルAIに読み込ませて感情分析やトピック分類を行い、その結果をグラフ化ツールで可視化する、といった連携も考えられます。
これらの連携は、研修コンテンツの制作プロセスを自動化・高度化し、担当者がより戦略的な業務に集中するための時間を生み出します。
AIの進化が研修に与える影響
AI技術は日進月歩で進化しており、その進化は研修のあり方そのものを変えていくでしょう。近い将来、以下のような研修が当たり前になるかもしれません。
- 完全パーソナライズドラーニング
- AIが受講者一人ひとりの理解度や興味に合わせて、リアルタイムで研修内容や難易度を変化させます。ある受講者には基礎的な解説を、別の受講者には応用的な課題を提示するといった、完全な個別指導が実現します。
- VR/ARシミュレーション研修
- 言語モデルAIが生成したシナリオに基づき、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)空間でリアルなロールプレイング研修が行えるようになります。例えば、AIが生成した多様な性格の顧客アバターを相手に、クレーム対応のシミュレーションを何度も繰り返す、といったことが可能になります。
研修担当者は、こうした技術動向を常にウォッチし、新しいテクノロジーをどのように自社の研修に取り入れられるかを考える、未来志向の視点が求められるようになります。
ユーザーフィードバックを活かしたAI利用法
AIを最も効果的に活用するための究極の秘訣は、「人間からのフィードバック」をループさせることです。AIは万能ではなく、人間からの具体的な指示や修正があって初めて、その能力を最大限に発揮できます。
研修プロセス全体に、このフィードバックループを組み込みましょう。
- Plan (計画)
- AIを使って研修資料のたたき台を作成する。
- Do (実行)
- その資料を使って研修を実施する。
- Check (評価)
- 研修後にアンケートやテストを実施し、受講者からのフィードバック(定性的・定量的データ)を収集する。
- Action (改善)
- 集まったフィードバックをAIに読み込ませる。プロンプトは
「以下の受講者アンケートの結果に基づき、次回の研修資料で改善すべき点をリストアップし、具体的な修正案を提案してください」といった形です。
- 集まったフィードバックをAIに読み込ませる。プロンプトは
- Re-Plan (再計画)
- AIの提案を基に、人間が最終的な判断を下し、次回の研修資料を改訂する。
このサイクルを回し続けることで、AIはあなたの組織や受講者の特性を「学習」し、回を重ねるごとに、より的確で質の高い提案をしてくれるようになります。AIを単なるツールとしてではなく、共に成長するパートナーとして捉えること。それこそが、これからの時代に求められる研修担当者の姿なのです。
オンラインでの研修にWisdomBase
 https://wisdombase.share-wis.com/
https://wisdombase.share-wis.com/
WisdomBase(ウィズダムベース)は、クラウド型のeラーニングシステムとして、教材の管理から学習状況の可視化までを一括で行える次世代型LMS(学習管理システム)です。
直感的なユーザーインターフェースと多彩な機能で、企業研修の効率化と成果向上を同時に実現。導入直後から社内教育をスムーズに運用できるよう設計されており、業務負担の軽減と学習効果の最大化を支援します。
1. わかりやすいUIと統合型の運用機能
コースの作成、進捗管理、成績の確認までをすべてWeb上で完結。受講者も管理者も迷わない画面設計で、初日からスムーズな運用が可能です。結果として、受講率の向上と管理業務の効率化が同時に叶います。
2. あらゆる教材形式に対応した柔軟性
動画、PDFなど、幅広いコンテンツ形式を簡単にアップロード可能。インタラクティブな教材作成もスムーズに行えるため、最新のトレンドに即した学習体験をスピーディーに提供できます。
3. カスタマイズとサポートで企業研修を強力に支援
導入後も、経験豊富な専任スタッフがオンラインで継続支援。トラブル対応はもちろん、権限の細かな設定もお任せいただけます。事業の成長に応じたスケールアップも柔軟に対応可能です。
4. 学習状況の可視化と継続的な改善
ダッシュボード上で受講データやテスト結果をリアルタイムに分析。得られた学習データをもとに教材の改善が行えるため、研修効果を継続的に向上させることができます。これにより、教育コストの最適化とスキル向上の両立が可能になります。
eラーニングシステムの導入をご検討中の方へ。
WisdomBaseなら、運用のしやすさと学習効果の両立を実現できます。
「社内教育をもっと効率的にしたい」「自社に合ったLMSを探している」とお考えの方は、ぜひ資料請求やお問い合わせフォームからご相談ください。
wisdombase.share-wis.com
wisdombase.share-wis.com

