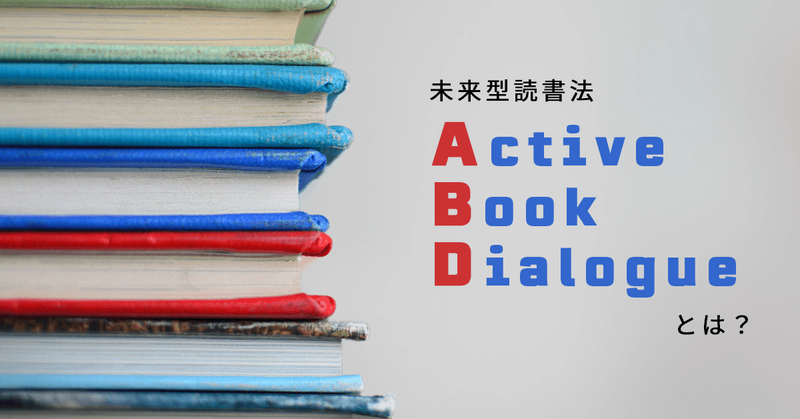
ご存知でしょうか。
「読書といえば、一人で黙々と一冊の本を読むもの」
この誰もが持っている認識を覆される読書法が、最近話題を呼んでいることを。
以前、「Z世代の新入社員に読書させるにはどうすれば良いのか」という記事をこのブログでご紹介しましたが、今回まとめているABD(Active Book Dialogue: アクティブ・ブック・ダイアログ)は、新入社員に読書の良さを気付かせるためにも、とても良い方法なのです。
今回の記事が「社員にもっと読書をしてほしい!」とお考えの人事担当者や経営者の方のご参考になれば幸いです。
ABD (Active Book Dialogue) とは何か
未来型読書会とも呼ばれるABD。
この読書法の大きな特徴は、一冊の本を複数人で分担して読むことです。
三和研磨工業株式会社の代表取締役である竹ノ内 壮太郎氏が開発したと言われています。人材開発の手法としてファシリテーションを活用する中で誕生したとのことです。
ABDは以下の流れで進めていきます。
- 参加者それぞれが読むパートを決める
- 制限時間を決めて、一斉に自分のパートを読む
- 自分が読んだ箇所を要約して発表する
- 参加者間でディスカッションし、各パートの理解を深める
一つの本を分けて読むため、必然的に一人の読む量は少なくなります。普段は画像や動画による情報のインプットに慣れていて、長い文章を読むのが苦手と言われているZ世代にはピッタリの読書法と言えるのではないでしょうか。
実施する際の具体的な流れとポイント
準備物
- B5サイズの紙(一人につき8枚)
- 養生テープ
- 水性の黒ペン(人数分)
- 模造紙
- 75mm × 75mmの付箋
- 話す人を明確にするためのトーキングオブジェクト(人数 ÷ 4個)
- ロール付箋紙
- セロハンテープ
チェックイン
ABDを始める前に、まず話しやすい雰囲気作りからスタートします。
参加者一人ずつが順番に自分の名前、今気になっていること・感じていることを1分程度で話していきます。新人研修の場合は、話す内容を参加者の趣味や最近気になっているものなどに変更し、さらに打ち解けやすくするのもオススメです。
一通り話し終わったら、今回の本の選定理由や全体の流れなどを説明しましょう。その際に「人の話は遮らず最後まで聞く」「時間を守る」などルールがあれば一緒に伝えておきましょう。
本を分解する
次に、本を15~20ページずつに分解します。
研修の参加人数によっては、ページ数を増やしたり、章ごとに分けても良いでしょう。
分厚い本や人数が少ない場合は数回に分けて実施するのもいいかもしれません。
分解の際は、本を電子レンジで30秒ほど温めるのがオススメです。糊が溶け、簡単に分解することができます。
担当ページを割り振る
わけたページを割り振っていきます。割り振り方は自由です。
ランダムに割り振るのであれば、くじなどで選んでみるのも場を盛り上げる意味ではおすすめです。
難しい部分がある本の場合は、その分野に詳しい人にその部分を担当してもらうのが良いでしょう。
担当箇所の読み込みと要約
30分〜1時間くらいで各自担当したページを読み込み、要約します。
時間設定は本の難易度や割り振ったページ数によって調整しましょう。
要約はB5用紙に6枚以内で太字の黒ペンでまとめましょう。1枚につき5行以内、1行10文字程度でまとめると発表の際に見やすいです。文章だけでなく図やイラストの使用もOK。
読んだ部分の中で著者が訴えようとしていること・自分自身の学びになった点などを中心に要約してもらうと良いでしょう。
要約が終わったら、でき上がった紙を壁に貼り発表の準備をします。
各自の要約を発表
一人2分ほどで要約した内容を発表します。
ここで大切なのが著者になりきって話すこと。そうすることで著者が身近な存在に感じられ、本の内容が入ってきやすくなります。発表時は、タイマーを利用して1分経過後に合図→終了時は音を鳴らすなど時間管理をしっかりしましょう。
発表を終え次の人と交代する際は、ハイタッチをするといったルールを取り入れるとチームの連帯感が生まれやすくなります。
全員の発表が終わったら、二人一組で壁に貼られた紙を見ながら対話する時間を設けます。二人一組で見て回ることで、気になる箇所を話し合うことができ、会話を通じてより理解が深まるという狙いもあります。。気になる点があれば明るい色のペンで印をつけていきます。
気付きを生み出す対話
続いて4名ほどのグループに分かれて本の内容について30分~1時間ほど対話をします。
ここで大切になるルールが、浮かんでくる問いを書いてもらうこと。些細な疑問でも、探求したいことでも何でも構いません。付箋に問いを書いてもらい机の上に用意した模造紙に貼っていきます。その後は、出てきた意見を模造紙に書き出しつつ対話をしてもらいましょう。
こうした対話では、どうしても話が脱線してしまいがちです。そのためABDでは、疑問を書いた付箋や、壁に貼ってある要約の部分を指しながら話してもらうことを推奨しています。
最後に、グループで話し合った内容を全体に共有して終了です。
どんな効果が見込めるのか
ABDは、通常の読書に比べ深い気付きと学びを得ることができます。また、全員が同じ本を読むことで同じレベルの知識を持つこととなり、共通基盤を作ることができ、チームとしての力や連帯感が向上します。
さらに、自分とは異なる人の本の読み方や物の見方に触れることで、個人の多面的な成長に繋げることが可能です。これが新入社員研修としてABDを強くオススメしたい理由です。
本を読むための集中力・内容を要約する力・発表のためのプレゼン力・コミュニケーション力など、社会人として持っておきたい基礎スキルを網羅的に向上させることができます。
このように、チームとしての連帯感を強めつつ、個々の能力を上げることもでき、読書を好きになるきっかけとなるかもしれないABD。
早速、貴社の研修に取り入れてみられてはいかがでしょうか。
WisdomBase(ウィズダムベース)なら、安全な研修動画配信システムをカスタマイズ構築できます

オンライン研修の実現にも最適な、WisdomBase(ウィズダムベース)
WisdomBaseなら、今回紹介したABDを事前に説明するための動画など、研修担当者が制作したオリジナル動画を取り入れた独自の新入社員研修をオンラインで管理することができます。学習状況の進捗把握や習熟度テストの実施など、企業研修に必要な機能を網羅。EdTechベンチャーならではの柔軟性とスピード感で、追加機能作成にも柔軟に対応。
一般的なクラウドサービスではなく、事業会社さま及び代行会社さまの自社サイトセキュアな状態でシステム構築。貴社の資産として永続的的にご利用いただけます。ご要望がありましたら些細なことでもお聞かせください。お問い合わせはこちらからお気軽に 😀

